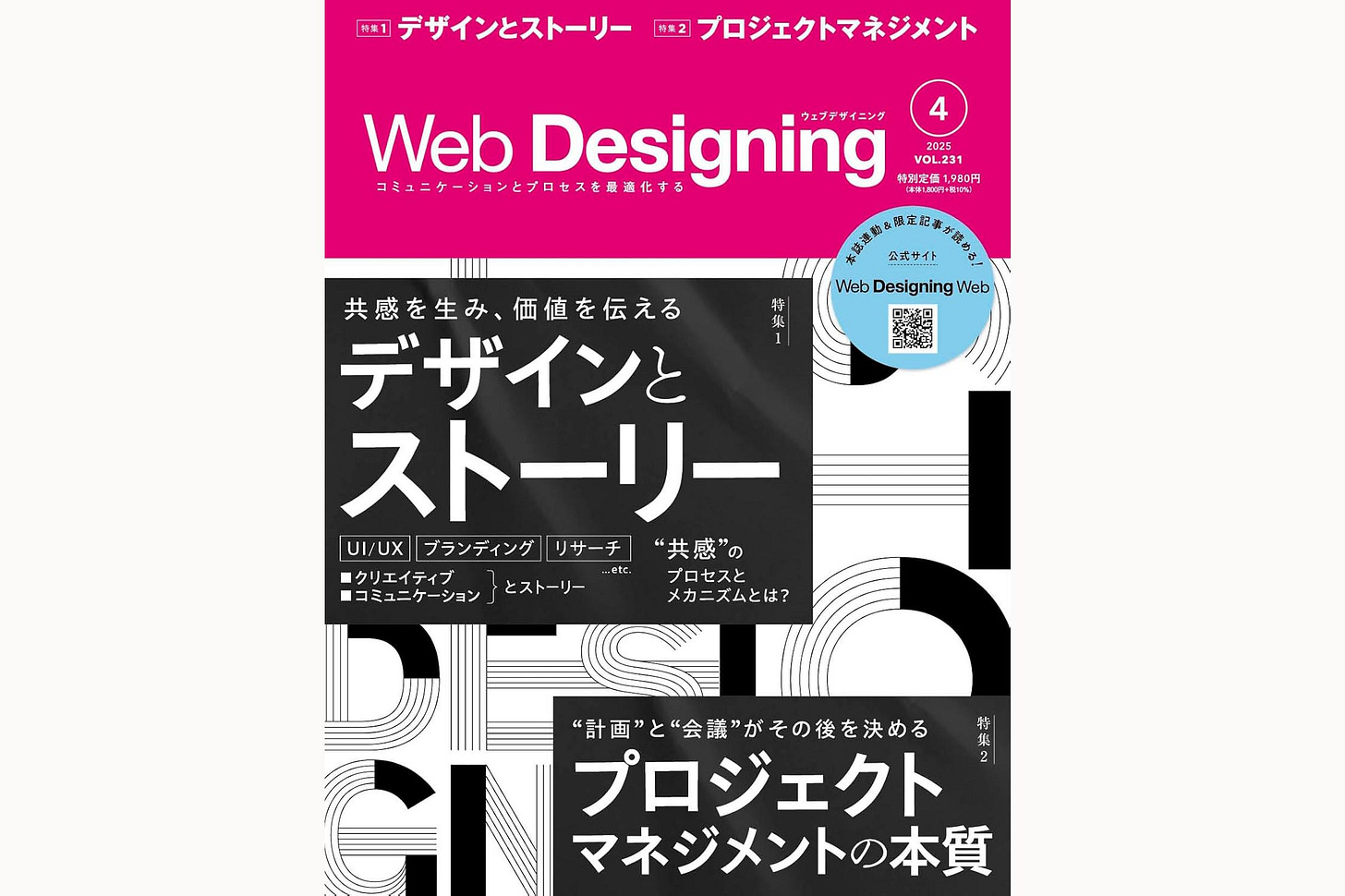世界中に広がる「アイデア」は、いかにして生まれるのか? | 川村真司さん〈1/2〉【デザインの手前×Web Designing】
「デザインの手前」は、デザインに関わる編集者2人がさまざまなクリエイターとともに、デザインの本質的な価値や可能性についてお話しするトークプログラム。ニュースレターでは、最新エピソードの内容をテキスト化してお届けしています。雑誌『Web Designing』との共同企画2回目のゲストは、クリエイティブディレクターの川村真司さん。前編では川村さんのクリエーションの核となる「アイデア」の話を伺いました。
デザインにおける「アイデア」と「ストーリー」
原田:今日は、雑誌『Web Designing』との共同企画の2回目になります。ゲストは、Whateverのチーフ・クリエイティブ・オフィサーでクリエイティブディレクターの川村真司さんです。よろしくお願いします。
川村:よろしくお願いします。
原田:大変ご無沙汰をしております。
川村:ご無沙汰しています。前回お会いしてから10年ぶりくらいかもしれないですね。
原田:最初に川村さんとお会いしたのは、おそらくインタビューをさせていただいた時だったと思いますが、もともと海外で活動されていた川村さんが日本に戻ってきて、伊藤直樹さんたちと東京でPARTYを立ち上げるちょっと前くらいにお話を伺ったような記憶があります。
川村:そうかもしれないですね。
原田:あれが2010年くらいだった気がしますが、実は山田さんはもともといらっしゃった『PEN』でも川村さんに取材しているんですよね。
山田:そうですね。
原田:すっかり忘れていたのですが、その時も僕が取材を担当させて頂いていたみたいです。
川村:おぉ、なんてことだ!
原田:10数年ぶりの時を経て、またふたりでやって来ました(笑)。
川村:同窓会的なノリになりすぎないように気をつけないとですね(笑)。

↓こちらからポッドキャスト本編をお聴きいただけます
▼Apple Podcast
▼Spotify
↓続きもテキストで読む
原田:まずは川村さんのプロフィールをご紹介させていただきます。川村真司さんは、Whateverのチーフ・クリエイティブ・オフィサーです。世界各国のクリエイティブエージェンシーでクリエイティブディレクターを歴任された後、2011年に東京でPARTYを設立されました。 その後、PARTY NEWYORKおよびPARTY TAIPEIの代表を務め、2018年にクリエイティブスタジオ・Whateverをスタートしました。 数々のグローバルブランドのキャンペーン企画を始め、プロダクトデザイン、テレビ番組、ミュージックビデオの演出など活動は多岐にわたり、カンヌライオンズをはじめ、国際賞を100以上受賞されています。
これまでに手がけた主な仕事として、SOUR『日々の音色』、安室奈美恵『Golden Touch』などのミュージックビデオ、NHK Eテレ『テクネ 映像の教室』、NHK連続テレビ小説『スカーレット』オープニングタイトルバック映像、Nike Unlimited Stadium、ストップモーション時代劇『HIDARI』パイロットフィルムの原案・脚本・監督などをされていらっしゃいます。
そんな川村さんにこれから前後半2回に分けてお話を伺っていきます。今回は、『Web Designing』の特集テーマが「ストーリー」ということなんですよね。
五十嵐:そうです。「デザインとストーリー」ですね。
原田:後編では、そのストーリーについて色々お聞きしたいと思っているのですが、川村さんのクリエーションの特徴として、もう一つ大きな要素として「アイデア」の面白さや強さがあると思うので、前半は「アイデア」の話をお伺いしたいなと考えています。「アイデア」と「ストーリー」というのは、対象的な2つのデザインに関連する要素だと思っています。「アイデア」というのはどちらかというと瞬発的なイメージがありますが、一方で「ストーリー」というのはそれを持続させていくようなイメージがあるなと。
川村:なるほど。
原田:両者を対比させるのも面白いと思ったので、今回は前半で主にデザインにおける「アイデア」の話をお聞きして、後半は「ストーリー」の話を聞いていきたいなと思っています。
川村:がんばります。
時代を予見していた「日々の音色」
原田:僕が最初に川村さんにお話を伺った時は、SOURの『日々の音色』というミュージックビデオをつくられていた時期です。色々な人がWebカメラで撮った映像をグリッド上に配置してひとつのミュージックビデオにするという映像で、これを15年くらい前につくっていたわけですが、その後コロナがあってオンラインでコミュニケーションすることが当たり前になり、いま見るとまた違った味わいがある作品だなと感じます。
川村:そうですね。この作品のようなものを日常的に見る機会が増えているというか、Zoomでみんなで一緒の画面にいるようなことが普通になりましたよね。時代を先取りしたというと言い過ぎかもしれないですが、ちょっと予見はしていたのかなと。そういうものづくりができて良かったなと思いますね。
山田:まさに原田さんと取材させて頂いた作品でしたよね。当時はだいぶ早かったというか。
川村:そうですね。YouTubeもまだ出てから数年くらいの時期だったと思います。古い作品なのでご覧になっていないリスナーの方も多いと思いますが、オンラインにまだあるのでぜひ見ていただきたいですね。
原田:コロナ禍で外に出られなくなって、Zoomを使ったクリエイティブも色々と出てきましたよね。そういう意味ではある種時代を予見していたなと。
川村:僕らの時は頼まれてはいない中でやったわけですが、実際にパンデミックのようなことが起こるとそういう形でしかクリエーションができなくなって、必要に駆られてみんなクリエイティブになったところがありましたよね。僕らとは全然違う形でノーミーツさんのような劇団が現れたり、制約による表現のジャンプというものが凄くあった時期だったなと思います。
山田:「日々の音色」が2009年の発表なので、ちょうどその10年後にコロナが起こったという感じだったんですね。
原田:やはり10年も経つと、SkypeがZoomになったり、ツールも変わっているわけですよね。
川村:いまならZoomを使ってライブでやってみるとか、もう少しトリッキーなこともできたかなと思いますね。アイデアとデザインと言うか、この場合はテクノロジーとも言えるのかもしれないですが、その掛け算が凄く上手くいった作品だったのかなと思います。それがMTVなどでも結果的に流れることにはなったのですが、オンラインのYouTubeというプラットフォームで流すというのもオーディエンスにとっても凄くシナジーがあるメディアの選び方で、「オンラインで繋がれるといいよね」と思ってくれるクラウドのところにそういう表現を公開したところがありましたね。
ACC「デザイン部門」審査委員長として
原田:いま少しお話に出た制約やツールの話というのも「アイデア」と密接につながっている気がします。その辺の話も追々聞いていきたいのですが、その前にまずは川村さんが「デザイン」というものをどう捉えているのか、川村さんのデザイン観についてもお聞きしたいなと思っています。最近川村さんはACCのデザイン部門の審査委員長をされていらっしゃいますよね。
川村:本当に僕で大丈夫ですか? という感じなのですが(笑)、やらせていただいていて、無事1回目が終わったばかりです。
原田:ACCでは、広く色々なデザインを評価されていますが、主にテクノロジーやデジタルの領域で色々なクリエイティブをされている川村さんご自身は、デザインというものをどのように捉えているのかということを聞いてみたいなと。
川村:これは永遠に悩み続けて死んでいくんだろうなと思っているのですが、ひとつの定義がしにくいものですよね。本当は確固たる意味や語義があるような気もするのですが、色んな文脈で使われすぎてしまっていて、多分話す人話す人必ず若干ズレるというか。僕の最近のフィーリングとしては、来年変わっている可能性もあるのですが(笑)、カテゴリや名詞で表現されるものではなく、先ほどから出ている「アイデア」という言葉に紐づいていて、「アイデアを形にする行為」がデザインだと捉えています。
原田:なるほど。
川村:だからデザインというものは動詞として捉える方が自分としてはすんなり入ってくるものだったりするんですよね。例えば、「デザイン部門」みたいなアワードだと、ポスターや新聞、パッケージングなどのイメージがありますが、それは一義的、一面的なデザインの捉え方な気がしていて、本質的にはもう少し大きな話なのかなと。アイデアというものがあった時に、それをどういう形にして世の中に具現化すればいいのかという思考プロセスとその結果を含めて、おそらくそれは有形のものも無形のものもあったりするのですが、その行為がデザインということなのかなと自分の中で納得しようとしているところがありますね(笑)。
だから、「デザイン部門」と言ったところで、「それって『なんでも部門』じゃん!」「WHATEVERじゃん!」という気にもなってしまうのですが、だからこそ僕は楽しんでやらせてもらっているところはありますね。
原田:デザインと言うとどうしても成果物を見られがちですが、それはまさに名詞的にデザインを捉えるということだと思います。川村さんのお話だと、アイデアを生み出すところからそれを具現化するまでの方法論、定着させた後にどこにどういう風に届けるのかということも含めて、一連のプロセス自体を動詞的に捉えることが大事だということだと思います。ただ一方で、審査はどうしても成果物で判断されがちじゃないですか。その中で、今回デザイン部門の審査をするにあたって、審査委員長としてどんなところをポイントとされていたのでしょうか?
川村:まさにそこが難しいところなんですよね。「デザイン部門」はまだ3年目のカテゴリで色々改善点も内包しているのですが、やろうとしているアンビションは最初に審査委員長を務められた永井一史さんの時から明確で、広義のデザインさらに言うとプロジェクトを評価するようなやり方にしたいということがありました。いま我々が言っていることは、デザインされたモノだけではなくてその前後、まさに「デザインの手前」に近いのですが、プロジェクトの成り立ちやプロセス、意義みたいなものから、モノやシステムが出た後のソーシャルインパクトなどを全体的に見て評価しましょうということです。なんとなくみんなわかるようなわからないような感じなのですが(笑)、受賞作品の集合体を見ていただくことでなんとなく感じてもらえるような形でやっているというのが実体ですね。今年は医療機器がグランプリを獲っている一方で、不二家のブランディングや日本科学未来館の常設展で僕も関わった「老いパーク」なども入っていたり、色々なんですよね。
原田:凄く幅が広いですよね。
川村:それはそれで僕が思い描くデザインの世界観はとらまえられているのかなとは思うのですが、果たしてそれが応募者にとってわかりやすいかどうかは不明だし、「医療機器が出てきたら勝てねぇよ」と思う人も多いと思うんですよね(笑)。 ただ、総体で見ようとなった時に今年はやっぱり医療機器が強かったですね。
山田:同じ土俵に乗せていいのかという問題がある一方で、俯瞰的に見ることで社会が見えてくるところもありますよね。
川村:そうですね。僕としてはやっぱりそっちの気づきの方が面白いなと思うし、雑多な中での強度をある程度指し示すことで、目指すべきクオリティが見えやすくなるみたいなところはあるのかなと。閉じた枠の中で井の中の蛙的にやるのではない「強さ」というのが浮き彫りになる気がしていて、デザイン部門がACCの中でそういうカオスな場になるといいなと思ってはいるんですけどね。
アイデアは誰にでも開かれている
原田:前半はアイデアの話を聞きたいと思っています。Whateverのサイトを見ると色々なプロジェクトが紹介されていますが、特徴として「IDEA」というクレジットが、「ART DIRECTION」「DESIGN」などとともに記載されていますよね。そこには意思を感じるというか、他でそういうことをされているところは少ないと思うのですが、川村さんの中でデザインにおけるアイデアの位置づけや重要性をどう捉えていらっしゃいますか?
川村:これは僕の個人的な好みの話で真理とかではないと思うのですが、僕個人としてアイデアを考えることが凄く好きなんですね。もちろん、それを最高の形に定着したいからデザインもがんばるのですが、10点満点中7点くらいはアイデアで決まると実は思っていて。ただ、そこから残りの3割のデザインを良くしていくことが非常に難しいのですが、それくらいアイデアを重要視しています。
面白いことに、アイデアというのはその重要度に比べて、色んな人がそこに貢献しやすいものでもあって、たとえばうちのお母ちゃんがたまたまポロッと言ったものが凄い良いアイデアだったということがワンチャン起こり得る領域なんですよね。デザインというのはどうしても職人的なスキルや経験値が如実に結果に現れる行為なのですが、アイデアに関してはまぐれ当たりも含めてワンチャン誰でも貢献できる部門なんです。うちの会社でもアイデアはみんな考えるし、もちろん忙しくてできないことはあるのですが、インターンでもプロデューサーでもデザイナーでもエンジニアでもアイデア考えようぜということを推奨していて。実際、インターンの子が出したアイデアが、もちろんチームワークでブラッシュアップはするのですが、採用されて形になっているケースもあって。アイデアというのは凄く重要なものなので、それが誰のものだったのかということはクレジットできていないことがそもそもおかしいと思っていたんです。よくある話として、有名デザイナーの仕事というのは実際にその人が何もやっていなかったとしてもその人の仕事になってしまうケースというのがあるじゃないですか。不可抗力的に「あれオレ」みたいな状態(笑)。それをわざとやっている悪いヤツもいますが、それがもう気色悪いというか凄い嫌じゃないですか。だから、不可抗力でその人のものになってしまうんだったら、せめてアイデアはこの人だったということをきちんと刻んでおけるというか、全体を見た時にもフェアに「あれは川村さんの仕事だったけどアイデアは僕です」とかも言えるじゃないですか。そういうことをオープンにしておきたいなと思ったんですよね。それによってアイデアの価値がもうちょっと顕在化してほしいということもあるし、メンバーそれぞれのキャリアにも貢献するじゃないですが、それが明確になっていることが凄く良いんじゃないかと思って、うちの会社では細々とそれをやるようにしていて。できれば他の企業も取り入れてくれたらいいのになと思っています。
原田:そういう意味で「アイデア」というのは本来民主的なものであるはずですが、一方でクリエイティブやデザインの世界に関わっていない人からすると、クリエイターと呼ばれる人たちは「普通は考えつかないようなアイデアを出す人たち」というイメージがあって、アイデアというのがクリエイターの神秘性と紐づいているところが多いような気もしています。
川村:なるほど。神秘的なものに思っていただけるのは、商売する側としてはありがたいですけど、意外とロジカルに考えているというのがありますね。これは人にもよると思いますが、僕とかうちの会社では全部ロジカルに逆算して説明もできると言うか、意外と色んな要素を丁寧にプログラミングのように組み立てて、課題を紐解いて最適解を出すということをしていますね。
山田:例えば、安室奈美恵さんの『Golden Touch』などを見ると、誤解を招くかもしれませんが、しようもないといえばしようもないアイデアというか(笑)。でも、それが世界的に凄く話題になったわけじゃないですか。モニターに指を当てておけば、自分も参加できるという本当に子どもが思いついてもおかしくないようなアイデアなんだけど、それを大手を振って真正面からクオリティ高くつくっていくということもやられるし、もちろんテクニックやテクノロジーを使わないとできないこともたくさんやられている。アイデアの中にも凄くシンプルなところからスタートするものもあれば、しっかり構築されているものもあって、川村さんの仕事はそれが色々混ざり合っているのが面白いなと。
川村:それはとても面白い評価ですね。あまり人からそう言ってもらえる機会はないので。でも、なるべくシンプルにしたいなとは思っているんですけどね、常日頃。誰でも共感できるストーリーとか、誰でもハッと驚けるアイデアとかね。だから、「子どもが考えるような」というのは凄い褒め言葉で、ある種社会の知見がない子どもでも思いつけるし、面白いと思うようなものに、ロジックが積み重なった上で戻ってたどり着けたりすると、それは強いアイデアにあることが多くて。インタラクティブにタッチするのではなくて、本当にただ触ったフリができるビデオをつくろう、「タッチ」だし、みたいな。後で聞くとアホみたいなんだけど、意外とそこにたどり着くのは結構大変というか、100とか200とか考えた中でそこにいけたりすると凄く強いものになるし、誰にでも届くようなシンプルでユニバーサルなアイデアを、正しいデザインの仕方で形にしてあげると全世界でバイラルするようなインパクトを出せたりするんですよね。それなら、最初からその可能性を見越してなるべく全世界の老若男女誰にでもわかるようなアイデアにしておきたい。ワンチャンそういう広がりがあるようなものにしておきたいと思ってつくっているので、なるべく子どもでもわかる、思いつくと思われるくらいのシンプルさで、でも見たことがなかったみたいなところを発掘できると、「キター!」みたいな。
五十嵐:少し『WebDesiging』の方に寄せさせていただくと、それこそ「日々の音色」とかWeb界隈や『WebDesiging』の読者の中で、やっぱり凄いなとなったと思うんですね。当時やっぱりインターネットは表現媒体のひとつで、絵画で言えばキャンバスみたいなものとして、プラットフォームとして機能している面があったと思うのですが、いまはどちらかと言うとインターネットが普及してインフラになった中で、アイデアというのが当時と同じ意味合いなのかというと、Webの文脈で考えると少し変わった部分もあるのかなと思っているところがあるのですが、それでもいまのお話しで「老若男女にわかるように」というのは凄く普遍的なものがあるんだろうなと思いました。
原田:さっきも仰っていましたが、タイムレスではあるけど最新のテクノロジーとも並走していくという川村さんのアイデアの考え方はやっぱり面白いなと思って聞いていました。
川村:ありがとうございます。ツールに関しては、もう本当に好みの問題で。ただ、「既存のメディアをこういじったら見たことがないものができそうだ」とか「このツールをこんなものに使ってみたらよくわからない別のものになった」というのが個人的には結構好きで。それが驚きやすいと言うか、やっぱり新しいもの、見たことないものをつくる近道は、結局つくり方やツールをちがうものにするというのが一番手っ取り早くて。それを個人的な趣味として入れられないかなと常々思いながらつくっているので、そういう表現が生まれやすいというか、そういうケースが結構多いのかもしれないですね。
良いアイデアを出し続けるためには?
原田:先ほどひとつのアイデアに至るまでに色んな別のアイデアも考えているといった話がありましたが、それはある意味ロジカルに考えるというか、ひらめきだけではないということですよね。子どもでも考えつけてワンチャン良いアイデアを出す可能性はあるとは言いつつも、その確率を上げていく方法があるわけですよね。
川村:まさにそれでしかないんですよね。アイデアを出すプロセスは多分ルーキー時代、新卒時代と実は変わっていなくて、単純にそのプロセスが超高速化されているだけというか。アイデアが突然落ちてくるというようなことではなくて、例えばこれまでは100案考えるのに1週間かかっていたところを、いまは10秒くらいでできて、もの凄いスピードで取捨選択ができている中で、それを選び上げてトーナメント式にやっていると言うか。いまなら1週間もらえたら1万倍精度が高いものにたどり着けているというか、凄い速さで反復横跳びをしている感じです(笑)。成長カーブって結局そういうことなんだなと。突然シナプスが未知の発火をするようになるという進化はなくて、経験と知識によってスピードアップするということなのかなと思いますね、アイデアに関しては。
原田:アイデアを出すための要素として、「経験」と「知識」というものが出てきましたが、一方で若い人ほど斬新なアイデアを出すといったイメージもあると思うんですね。経験や知識というものに対して、そうした「若さ」というのはどうなんでしょうか?
川村:どうなんですかね。僕は多分いまの方が面白いアイデアを考えられているとは思うんですけどね。ただ、若い頃は青いけど面白い企画というのを出せていた気もするし、若さゆえの勢いというのは当然あるし、失敗もしやすかったというか。そういうものにインベストできて、もっと失敗ができるような凄い野望あふれるプロジェクトみたいなものは若い頃の方がやれる機会があるから、そこでのトレードオフみたいなものはあるのかもしれないですね。
山田:例えば、YouTubeが広がってきたのは2008年とかそのくらいですよね。十数年前にそういうツールが出てきた時に「日々の音色」が生まれたわけですが、いまでもそういう面白さに対して目を向けていく感覚は全然変わらずというか、社会とつながっていられると思いますか?
川村:あまり変わってはいないですね。そういう意味では、興味のアンテナは変わらないし、やっぱり新しい価値観や視点に気づいてほしいというつもりでものをつくっていたりはするので、やっぱり受け手のことは意識しますね。それが個であったり、社会であったりすると思うのですが、トレンドとはまた違うんですけど、社会環境と言うんですかね、そういうものにはなるべく敏感でいたいと思っています。
原田:そういう意味では、「知識」「経験」に加えて、「好奇心」みたいものがアイデアを出し続ける上で必要な要素なんでしょうね。
川村:だと思いますね。やっぱりそれが一番大変というか、リクルーティングする時もやっぱりそこだけは育てられないので。うちの会社では「好奇心」というのを結構重要視していて、そもそもこの人はデザインは荒いけど好奇心がメチャクチャあるかどうかというところで、やっぱりその後の伸びが全然ちがったりするんですよね。ほっておいても勝手にアイデアを考えてつくってくれる人が好きですね。それが会社にとっていいのかはわからないですけど(笑)。デザイナーとしてはやっぱり大事な素養だと思うし、それがないんだったらやめた方がいいぞと言ってあげる方が良いなと思うくらいですね。
アイデアは課題意識から生まれる
原田:川村さんはWhateverのことを「考えて、つくれるチーム」であることが大事だと話されていますが、そことつながる話として、「アイデア」と「クラフト」の話もお聞きしたいです。アイデアというのはそれだけがあっても仕方がなく、しっかり定着させることが必要ですよね。そういう意味で、アイデアというのはある種デザインの「手前」にあるものだとも思えますが、手を動かしながら出てくる「アイデア」もあるような気がします。そういう意味で、「アイデア」と「クラフト」の関係についてはどう考えていますか?
川村:カタチという意味で言うと、やっぱり僕はアイデアありきで考えるので。当然つくりながら変わってくる部分もあるのですが、やっぱり伝えたいアイデアや物語に対して最適なカタチを模索するということをやっている気はしますね。例えば、ここにひとつのアイデアがあって、それを映像にした方がストーリーとして腑に落ちやすいのか、インタラクティブな体験にしてもらう方がいいのか、イベントをやるべきなのか、それとも本だったらプロダクトにした方が、価値への気付きが高いものになるのかといったことを考えながら選んでいくようなことが多いですね。
だから、クライアントからお題をもらって、オリエンとかブリーフを返す時なんかでもたまに全然関係ないものを返したりすることもあります。この課題には、CMつくってくれと言われているけどイベントの方が面白かったり、ROI高いですよと言ったり。大体通らなかったりするのですが、一応そういうものも提案する。健やかに課題と向き合うなら、実はこちらの方が的を射ていると思いますみたいなことを言わせてもらったりするケースは結構ありますね。
原田:少し話が戻ってしまいますが、クライアントワークとそうではない時ではアイデアの位置づけも少し変わるのかなと。クライアントワークであれば、まず課題があり、それに対するソリューションとしてアイデアがあり、その先にメディアが選択されるという流れがあるのかなといまのお話から理解したのですが、一方でクライアントワークでない場合は、課題ありきではなかったりするのですか?
川村:自社プロジェクトとコミッションワークをあまり分け隔ててはいないのですが、唯一違いがあるとするとまさにスターティングポイントで、課題が与えられて応えるのがコミッションワークで、自社プロジェクトではその課題から自分で見つけていくところがありますね。
原田:どちらにしろ課題ありきなんですね。
川村:課題はありますね。課題というと若干言葉が硬いのですが、問題意識や興味や好奇心があって、それがニアリーイコール課題みたいなところで、そこから始まることが多いですね。例えば、うちがつくったミントタブレットは課題設定からしていて、もう少し違う時間の計測方法はないのか、まったく違う時計をつくれないのかというところから始まっています。課題意識と興味は裏表のような感じですが、そこから始まって、時間通りに溶けるミントをつくり、1分と1分半で溶けるものをそれぞれつくりました。その課題を見つけるところは鍛えておかないと錆びてしまうし、実はそっちの方が人生の役に立つ。課題を見つける力こそクリエイティビティだと思ったりするくらい大事なことで、そこもまたニアリーイコールアイデアだったりするんです。
「アイデア」と「クラフト」の関係性
原田:アイデアを出す人と、それを形にしたり実装する人が分かれていることが世の中的には多いと思うのですが、先ほどの「考えて、つくれる」という話で言うと、川村さんとしてはそこは統合した良いとお考えですか?
川村:絶対的にその方が良いですよね。細分化されればされるほど、もともとあったアイデアの強さが減っていくんですよね。これはもう経験則上100%そうで、例えば戦略チームから下りてきて、クリエイティブチームに渡された段階で、ある程度ストラテジーも捨てられる部分があるし、アイデアを考えてつくってからもデジタルプロダクションに入れた時に全然予算にはまっていないとか、そんな技術はないですよというケースがあったりするんですよね。すべてのステージでちょっとずつ角が取られていってしまうので、アイデアを考える人たちとそれをカタチにする人たちは最初からひとつのテーブルを囲んでアイデア出しから一緒にいた方がいい。つくる人は別にアイデアを出さなくてもいいけど、それを聞きながらこれはできる、できないという判断ができるし、そうすることで失われるものを減らせるどころか、早めにわかることでもっと良いアイデアにできたということを技術側から言われて気づいたり、技術の人にできることを聞きながらアイデアがさらにジャンプアップすることもある。逆に、このタイミングでわかっていたら違うこともできたのにとか、提案に目一杯盛り込めるということもあって、それがつくるフェーズになっても凄くワークするんです。僕はよく山に例えてしまうのですが、なるべく高い山に登ろうと思うと。考えるとつくるが合致して、最初からグルグルなるべくフェーズやチームを分けずにやった方が確実に良いものになると思ってやっていますね。
山田:ちょっとウェットな言い方ですが、アイデアを愛している人たちが最後まで愛し抜いた方がいいと。
川村:本当そうですよね。人間同士のコミュニケーションではなにかしらがロスされるじゃないですか。受け渡しがある度に不可抗力的に何かが削られてしまうんですよ。そこはなるべく減らせるだけ減らした方が強度が高いものになるというのは真理かなと思いますね。それができない事情もわかるんですよね。組織的な事情だったり、ファイナンスや部門間の予算のやりくりとかも面倒くさいなと思うので可哀想だなとは思いつつ、なるべくうちはそうならないような組織づくりからしていて、なるべく自由に動き回れる状態を保とうとしている感じですね。
原田:例えばクライアントワークであれば、クライアントにアイデアの良さを理解してもらう必要があると思います。アイデアを人に伝える時の伝え方というのも、アイデアをゴールまで持っていくスキルとしては大切かなと思っています。それで言うと、先日開催された「渋谷パイロットフィルムフェスティバル」 というのもそのひとつの手段なのかなと思いますが、川村さんがアイデアを人に伝える方法として大事にしていることがあればお聞かせください。
川村:面白い視点ですね。そういう話をする機会がある時は、良いアイデアを出すだけではなく、アイデアを提案することにもアイデアが必要だということをよく言っています。このアイデアなら、踊った振り付け動画を見せた方が通るじゃんとか思うならそれを撮った方が良いんですよ。アイデアと言うほどでもない小さなアイデアでも、その面白いアイデアが実現する可能性が高まるなら絶対にそれを考えた方がいいですよね。最近多いのはプロトタイプを見せるということですよね。パイロットフィルムもそれに近いし、「HIDARI」もそういうことなのかもしれないですが、言葉で説明しても企画書だけ見てもわからないじゃないですか。「時代劇のコマ撮りで全部木でできているから血じゃなくておがくずが飛ぶんですよ」とか言っても、分かる人にはわかるけど、大抵の人はポカンとなる。それを5分でも映像にすることで、「凄い!こういうことか!」とやっとわかるんです。予算や時間の問題というのももちろんありますが、できる時にはそういう風に提示をした方がいいし、それは新しいアイデアであるほど重要になってくると思います。これはクラフトの話にもつながるというか、アイデアはさっきも話したように文章でも説明ができてしまうけど、最終的にはアイデアとクラフトやデザインの掛け算でものになるので、やっぱり出し惜しんではいけないというか、やれることは全部しないとなかなか通らないぞと。
原田:ここまで川村さんにデザインにおける「アイデア」の話を中心にお聞きしてきました。 後半では、2月18日に発売される『WebDesiging』4月号の特集テーマであり、アイデアをアウトプットに持っていくためにも必要なものであろう「ストーリー」について聞いていきたいなと思っております。次回もよろしくお願いします。
川村:よろしくお願いします。
最後までお読み頂きありがとうございました。
「デザインの手前」は、Apple Podcast、Spotifyをはじめ各種プラットフォームで配信中。ぜひ番組の登録をお願いします。
Apple Podcast
https://apple.co/3U5Eexi
Spotify
https://spoti.fi/3TB3lpW
各種SNSでも情報を発信しています。こちらもぜひフォローをお願いします。
Instagram
https://www.instagram.com/design_no_temae/
X
https://twitter.com/design_no_temae
note
https://note.com/design_no_temae