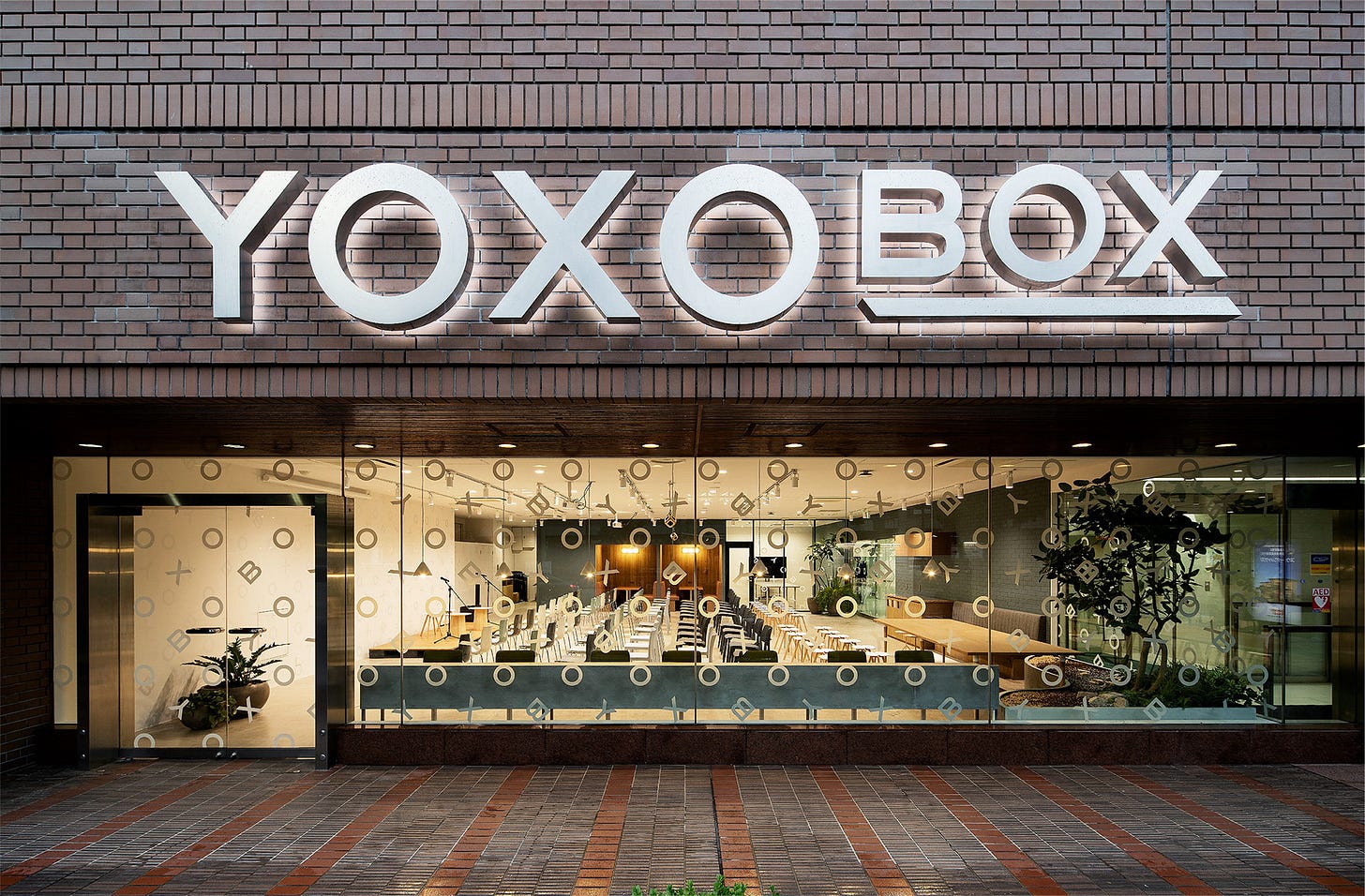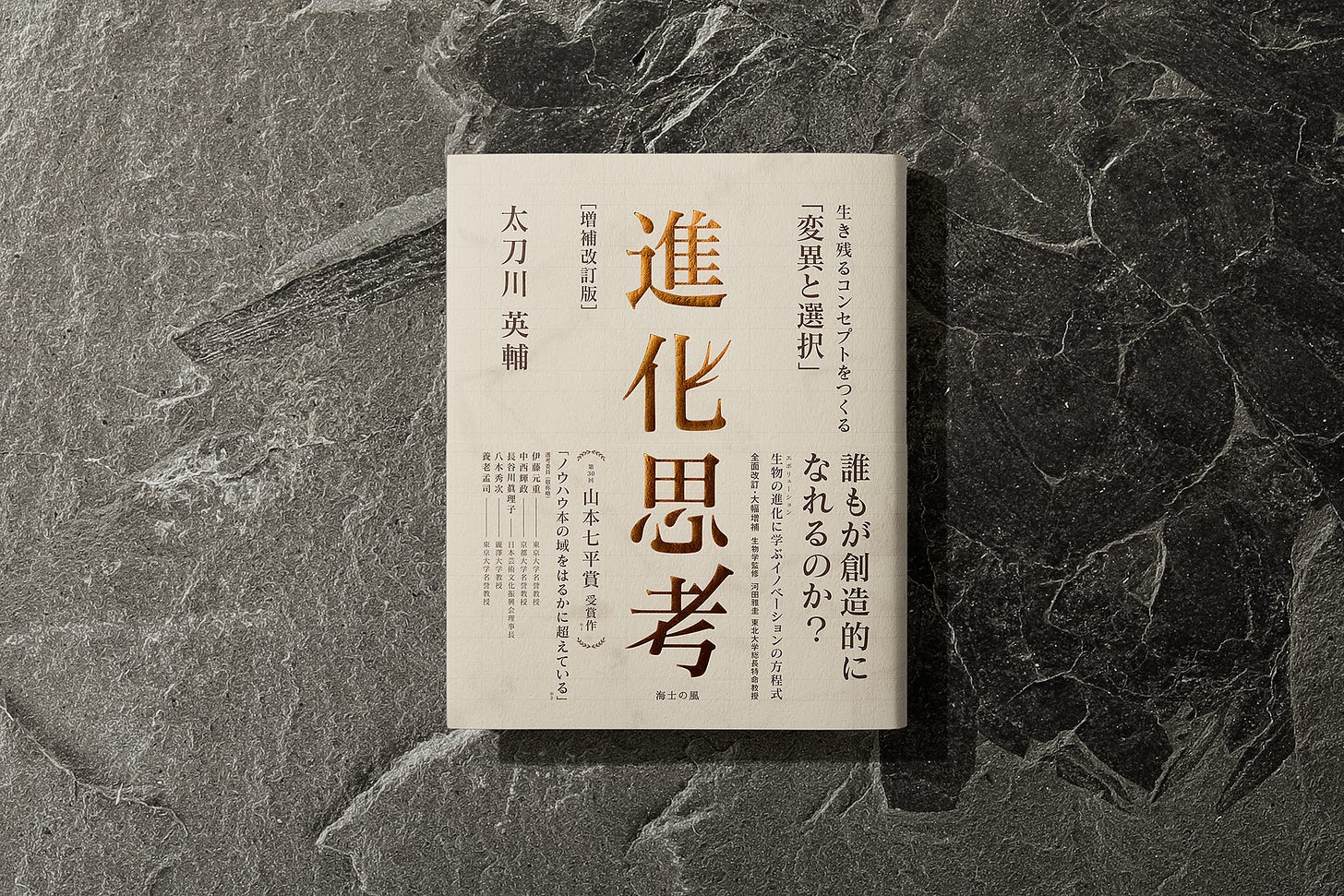領域を越境し、多様な人々と協働するには? | 太刀川 英輔さん〈2/4〉
「デザインの手前」は、デザインに関わる編集者2人がさまざまなクリエイターをお招きし、デザインの本質的な価値や可能性についてお話しするトークプログラムです。ニュースレターでは、最新エピソードの内容をテキスト化してお届けしています。デザインファーム・NOSIGNER代表の太刀川英輔さんをお招きする2回目のエピソードでは、太刀川さんがさまざまなプロジェクトで実践している領域の「越境」について聞きました。
NOSIGNERが実践する2つの越境
原田:今週もNOSIGNERの太刀川英輔さんをゲストにお招きしてお話を伺っていきます。前回は、デザインにおけるカタチの話をお聞きしましたが、今日のテーマは「越境」にしたいと思っています。
越境には2つの意味があって、ひとつはデザインの領域が広がる中でさまざまなジャンルを越境してデザインを手掛けていることがNOSIGNERなり太刀川さんのひとつの特徴だと思うので、そうしたデザイン領域の越境についてお話を聞きたいと思っています。もうひとつはデザインという分野を越境して、多様な分野の専門家と協働しているプロジェクトがNOSIGNERにはとても多いので、領域を超えて色々な人たちとコラボレーションしていくことについて聞いてみたいと思っています。
まずデザインの話から入ると、もともと太刀川さんのベースは建築ですよね?
太刀川:そうですね。大学院までは建築を学んでいました。
原田:例えば、建築やプロダクト、空間などをカバーしているデザイナーと、グラフィックやデジタル領域のWebやUI/UXを含めたデザインをカバーしているデザイナーはそれぞれいると思うんですね。でも、端的に言うと立体と平面みたいなところになるのかもしれませんが、これらを網羅的に手掛けているデザインファームというのは実はそんなに多くない気がしています。
太刀川:確かにそうかもしれないですね。これはもうライフストーリーみたいになってしまうのですが、大学院の時に隈 研吾さんの研究室にいて、結構建築をがんばっていたんですよ(笑)。建築が好き過ぎて、良い建築がつくりたいから、どこからどこまでが建築なのか、建築の良し悪しとは何なのかみたいなことに凄く興味がありました。
↓こちらからポッドキャスト本編をお聴きいただけます
▼Apple Podcast
▼Spotify
↓続きもテキストで読む
太刀川:昔からそういう風に考えすぎる人だったのですが、そうやって考えていくとだんだんゲシュタルト崩壊してきて(笑)。「これはどう考えてもインダストリアルデザインだけど建築な気もする」みたいなこととか、「非常口のサインとかもメチャクチャ建築的に機能している」みたいな。関係性というところにフォーカスがあたっていく中で、これはどのデザイン領域のものなのかということに対して差分がなくなっていくんですよね。はたと振り返ってみると、自分の手元にあるのは模型をつくる能力とプレゼンボードをつくるIllustratorの技術と、CGを描く3Dのモデリング能力とか、そういうことに建築の技術もわけられていくじゃないですか。そういうことをはたと振り返ってみると、これをちょっと変えるだけで家具がつくれそうだなとか、プレゼンボードをもっときれいにつくるためにはタイポグラフィを覚えないといけないんじゃないかとか。そうすると、スイススタイルとかブロックマンのグリッドシステムとかそういうものが妙にカッコよく見えるし、気になるぞと。その流れから派生して、Webデザインの世界で当時行われていたタイポグラフィをどうモーショングラフィック的に動かすかということの実験が色々行われている中で、これは建築のプレゼンボードと同じように見えるみたいな。いまはなきFlashとかを使って作品のプレゼンテーションをつくってみるとか、3Dのモーショングラフィックで作品の映像を切り出してみるとか、そういうことをやってみたらだんだんわからなくなっちゃったんですよね(笑)。でも、これは基礎がないなと。建築の基礎はあるかもしれないですけど、グラフィックやインダストリアルデザインの基礎がないから独学してみようと思ったのがちょうど大学院生の頃だったんですよ。
建築というのは結構学生コンペカルチャーだったので、ひたすらグラフィックとかインダストリアルデザインのコンペというコンペを調べて、そういうものに色々アプライしてみるようになったんです、コンペ荒らし的な(笑)。といってもそんなに序盤は荒らせてないのですが(笑)。そういうことをやり始めたのが、2004年くらいだったと思うので、ちょうど20年くらい前ですね。
太刀川:僕は昔からどちらかというと独学をしたいし、しがちなタイプの人間なので、それぞれのスキルを一つひとつ身につけてみるということが楽しかったんですよね。自分を筋トレをしてみようみたいな感じで、マイブームですよね。期間を決めているわけではないけれど、とにかくタイポグラフィが面白いと思ってタイポグラフィの本ばっかり読んだり、良い図面が書きたいと思って図面のことばかり考えるみたいなことを点で繰り返していって、そのマイブームが重なる中でだんだん定義がわかりにくい感じのデザイナーになってしまったんですよね(笑)。だから、全然意図せずに越境したという感じですね。面白いから。あとはツールが一緒だったからですね。建築がコンピューターと融合したり、DTPとかもそうですけど、凄くシームレスにツール上には壁というものが存在しなかったし、存在しないかのように学ぶことができた。学ぶモチベーションというものはあって、そういうところから越境していった感じでしたね。
プロジェクトがプラチナチケットになる
原田:デザインの領域がどんどん広がっていくと、それぞれの領域において洗練されていきますよね。そうすると、どうしても専門分化という現象が起きていくわけですが、そこまで各領域が洗練されていない、あるいは生まれていない状態にまで遡っていくと、一人のデザイナーがカバーできる領域がもう少し広かった時代というのがあったんだろうと思うんですね。太刀川さんはそこに立ち戻るではないですが、そういう人たちをある種ロールモデルとして見ているところがあるのかなという気がします。
太刀川:本当そうですね。独学をしていくということは、それぞれの文脈において何が重要だったのかということを自分なりに定義したり、学んでいったりすることでもあります。そうすると、現在活躍している人たちが参照している人たちというのがいますよね。例えば、建築で言えばコルビジェとかミースとかイームズとかバックミンスター・フラーとか色々いるじゃないですか。いま出した4人はみんな越境者なんですよね。コルビジェは画家だし、ミースは発明家で、フラーは数学者で、イームズはムービーディレクターでありサイエンスコミュニケーターであり家具のデザイナーですよね。だから本当は余地だらけであったと思うんですよね。いま建築の例を出しましたが、グラフィックで言っても例えば亀倉雄策さんなんてデザイン経営者の走りですよね。田中一光さんとかもそうだと思いますが、極めて越境的なアプローチがマスターピースをつくってきたと思うんです、本来。だけど、スタイルが洗練されていく中でやっぱり「型」化するんですよね。守破離の「守」が大きくなっていく。その中で守らなければいけないことというのは、本当に守らないといけないものなのか、それともその中で培ってしまったその象牙の塔の中でしか通用しないルールなのかは、本当に見返さなければいけないことなんだけど、それによって「越境しないことこそが本流なのである」という間違った概念が生まれると思うんですよ、長い時間軸の中で。本当の本流のリファーされている人たち、マスターピースはみんな越境者なのに。
原田:20世紀においてデザインが経済と密接につながってくると、どうしても市場の原理である程度デザインの領域がわかれていた方が色んな意味で都合が良いわけですよね。デザインで身を立てるということを考えるにしても、グラフィックならグラフィック、プロダクトならプロダクトの世界を極めていった方がある身を立てやすい状況があったり、色々な状況の中でデザインが細分化してきたのだと思います。一方で太刀川さんが考えるところのデザイン、1回目で話が出たように関係を紡いでいくということをしようとした時には、デザインの領域がわかれているとやりにくかったりするだろうし、いまは発注する側もWebはWebデザイン制作会社、グラフィックはグラフィックの会社とわけて発注しなくてはいけない状況というのもどんどん面倒くさくなっている気がするんですよね。そういう意味で、色んな角度からデザインを統合していくような流れというのが時代的にはまたいま来ているのかなという気もします。
太刀川:そう思いますね。やっぱり越境することによって、中途半端になったり下手になったらいけないと思うので、練習は絶対にしないといけないと当然思うし、それぞれの中でちゃんとやっていくことは大事だと思います。専門的なスキルセットに価値がないわけではないし、それはもう価値でしかないと思うんですよね。でも一方で、何とつなげたいのかとか、どういう目的のためのプロジェクトなのかとか、プロジェクトの目標や生み出そうとしている関係性に立ち戻った時にはデザインは手段でしかないので。同じ目的のためにウェブサイトが有効なら、家具をデザインする代わりにWebサイトをつくった方がいいかもしれないという時もある。それは選べるはずだし、そこからもうクリエイティビティは始まっているはずなんだけど、ダイレクションがないけれど、そのカタチはつくりたいみたいなところがあまりに強すぎると、前回の話にも出てきたようにスペクタクルではあるけど、あまり意味がないデザインに人は陥りやすいんじゃないかなと思うんですよね。
あと、これはもう結果論で、「面白かったから」ということなのですが、やっぱりクライアントも皆さんも何らかのプロフェッショナルで、そんな彼らから何も学ばないというのはとてももったいないことだと思うんです。一緒に文化をつくろうとか、お酒をつくろうという時に、その背景をちゃんと知ってみるとか、そこにつながっている関係性を理解してみて、そこに効くようなデザインをつくれると一緒にプロジェクトの成功を喜べるじゃないですか。その過程の中で最高の先生たちから学べるわけで、つまりプロジェクトがプラチナチケットみたいなものなんですよね。単にお酒を買って楽しむだけではなく、一緒に話し合ってああでもないこうでもないとやりながら、お酒の味にまで関われてしまう。すべてのプロジェクトでそういうチャンスがあると思うんですよ。それはとても面白いことだし、一緒につくるというのはそういうことだと思うのですが、その時にお酒にしても、素麺にしても、再生エネルギーにしても、それぞれの領域において越境せざるを得ないですよね。
デザイナーとしてそれぞれの領域で越境できることってなんだろうということを、それまでにそんなにケースが無いわけじゃないと思うけれど、まだケースが乏しい領域であったりした場合には、自分も少なからずその領域の人になるという姿勢が必要になるわけです。そうすると、どこからどこまでがデザインなのかもよくわからず、「興味があるから調べる」というプロセスが出てきますよね。それによっておそらく向こうも安心するんですよ。「なんかデザイナーって全然話ができない人かなと思っていたけど、この人凄いうちらがやっていることに興味があるっぽいな」と(笑)。しかも2、3週間したらちゃんと話ができるようになっていたりすると、多分教える側も面白いじゃないですか。僕が逆の立場でも面白いと思います。そういう中で仲良くなったり、時にはデザインの観点からいまこの領域に足りない方向性を提案することもできたりするんですよね。そういう中でこれも越境を目指してやっているというよりは、学んでみることが面白かったからということによって意図せず越境していた気がしますね。
専門領域の価値を社会とつなぐ
原田:いま自然とデザインの中の領域の話から、デザインの外の話にも繋げていってもらえたと思っているのですが、実際にNOSIGNERのプロジェクトではクライアントワークもそうですが、例えばパンデミックの時には「PANDAID」をご自身で立ち上げられたりもしていますよね。かつ、医療の専門家や編集的なスキルを持っている人まで色んな領域のスペシャリストを束ねたり、つなげていく役割を太刀川さんが担っているようなプロジェクトが多い気がします。
特にコミュニケーション領域のデザイナーというのは、色々な分野のデザインを手掛けるという意味ではもともと越境的な存在ではあると思うのですが、デザイナーとして意識的に領域と領域を繋ぐ役割を担っていくようなところが太刀川さんの立ち回りにはあるのかなと。一昔前になってしまいますが、オープンイノベーションが盛んに言われるようになり、中間領域的なところでイノベーションが生まれるという言説がありますが、それがなかなか上手くいかないのは間に入ってつなげる人の存在がなかなかいないからなのかなと。太刀川さんの動きというのはそこを繋ぐものでもあるし、実は色んな領域と関わるチャンスがあるデザイナーが担いやすい立ち位置なのかなという気がします。
太刀川:仰る通りで、プロジェクトを立ち上げる、コンセプトをつくるというのは極めてデザイン的な活動ですよね。旗をつくるとか「こっちでやってみたい」ということを投げかけるというアントレプレナーシップやリーダーシップと、具現化するためにコンセプトを考えることというのは表裏一体まではいかないけど、少なくともそういうリーダーシップのうちのひとつだと思うんですよ。そういう風に旗揚げをするとか。でも一人ではできないし、例えばPANDAIDにしても、偶然日本感染症学会の皆さんと別のプロジェクトをやっていたりしたのですが、自分がそんなに知っている領域ではない状況の中で、どういう風にアプローチをしていくのかと。その中で、さっきも言ったように色んな分野に興味があるから、それを知っているかもしれない人に興味を持ってお話を聞いてみるというプロセスがあった時に、彼らもそういう旗が立つなら一緒にやりたいとか、自分たちが持っている知恵には価値があると思っているけど、その発露の仕方が良くわからないということはよくあると思うんですよ。
そういう状況を僕は多分、NOSIGNERの旗揚げ当時くらいからなんとなく知っていたと思うんですよ。多分これは2つのことに由来があって、最初のグラフィックデザイナーとしてのプロジェクトは東京大学先端科学技術研究センターの仕事なんですよ。東大の先生で頭が良い素晴らしい方がいっぱいいるわけですが、彼らがやろうとしていることは専門用語に満ちていて、わかりにくいわけですよ(笑)。何を言っているかわからないけど、どうやら価値があるらしいと。これをどうやったらわかりやすくできるのかというのを、オープンキャンパスの設計に応用したりとか、そういうことを2007年にやっていました。要するに、どんなに素晴らしい研究をしている人でも、それぞれの領域の中で他者からわかってもらいたいし、わかってもらわなければなかなか広がらないというジレンマを抱えているということを知ったんです。
太刀川:また、最初のインダストリアルデザインのクライアントが徳島の木工のおじちゃんたちで、彼らが持っている技術は素晴らしいんですよね。クリエイティビティは素晴らしいんだけどそれをどうマーケットにつなげたらいいのか、どうやったら良いデザインになるのかというところがあったんですよね。それぞれの領域の中に宝物があるのに、少しブリッジされていないだけでそれが価値になりきれていないという状況って本当にたくさんあるんだなというのを最初の頃のプロジェクトで見せていただいたのが良かったと思うんですよね。実際に世の中というのはそいういうものじゃないですか。それぞれの人たちが素晴らしいものを持っているかもしれないけど、それが可視化されない。そこをブリッジしたいということって越境と同じような話ですよね。
原田:知らない領域に飛び込んでいくことにはある種の怖さも伴う気がします。デザイナーというのは色々な領域に関わる仕事とは言え、例えば医療や気候変動適応策など、太刀川さんが関わっている領域は専門性や難易度が高そうなイメージがあると思うんですね。そういうところにデザイナーが関わることにはやっぱり勇気がいると言うか、知らないことへの恐れを持っているデザイナーは結構多いのではないかと感じています。先ほどの好奇心の話にもつながるかもしれませんが、そこの一歩を踏み出すのか踏み出さないのか、踏み出したいと思うのか思わないのかも含めて、そこで大きくデザイナーの立ち振舞は変わってくる気がしています。そこの違いというのは何なんだろうなと。
太刀川:たしかに、何なんでしょうね。僕はデザインビリーバーなので、基本的には色んな領域にデザインが行きわたった方が良いと思っていて、まだ色んな領域に届いてない状況があると。一方で、デザインの中でデザインを語ろうとすると、「本当にデザインなんて役に立つのか?」と思わなくもないと思うんですよね。デザインの中にいるがゆえに。役には立つんですよ。でも、役に立て方を考えていなければ役にも立たないというのも事実だったりするし。
越境のポイントは「好奇心」
原田:デザイナーというのも専門家ではあるわけじゃないですか。そういう専門家同士で対話をするといったマインドも必要なんでしょうか?
太刀川:もちろん、自分がデザインの専門家であることに対して誇りは持った方がいいですし、それを持てるくらい研鑽を積んだ方が良いと思います。でも、どちらかというと知っているか知らないかよりも、好奇心があるかどうかの方が他の分野にトライする時には凄く重要だと思うんですよね。例えば、『進化思考』という本は日本生物進化学会の河田雅圭さんといういま会長を務めらている方が監修してくれていて、東北大学の進化学者の方ですね。他にも色んな方に関わっていただきながらつくった本なのですが、越境すると越境するなりに誤解をされることもあるし、凄く評価を頂くこともあって、そういうものだと思うんですよ、結局。何か新しいものやその領域の価値を別のところに使おうとした場合に、その領域のことを信じている人たちからすると応援する対象になるかもしれないし、「進化学にはそういう使い方があると思っていたんだよ」とか、「解剖学にはそういう使い方があると思っていたんだよ」と。そうそう、細胞学者の養老孟司さんたちからも『進化思考』は山本七平賞という賞を頂いたのですが。一方で「そんな使い方は間違っている!」といった声も起こるじゃないですか。それもわからなくもないし、そういうことだと思うんですよね。
領域のエッジで揺さぶるということがクリエイティビティにとって凄く重要だと思うのですが、それがリスクなんですよね、色んな意味で。そのリスクを避けるがゆえにその領域の一番安全なコンフォートゾーンの中で、あまりその領域の革新もできずに何となくこじんまりとしてしまうということが色んなところでサイロ化して起こっているのだと思うのですが、結局領域のエッジで失礼がないようにダンスするということが僕は一番重要だと思うんです。そのためには、やっぱり好奇心じゃないけど、ちょっと横にありそうな領域が「面白そうなので僕も弟子になるので教えて下さい」ということが凄く重要だと僕は思っています。そういう姿勢でいれば何か教えてくれる人はいますよね。それが色んな領域であるんじゃないかと思うんです。前回少し話したことを思い出しているのですが、ディテールの部分での革新か、領域の外側での革新か、どちらかに関しては永遠に価値が失われないのではという話をしましたが、その両方ともエッジでダンスを踊るしかないことだと思うんですよね、ある意味。いままでやられていなものをどうやってやるかということですから。いままでやられていることをやることが一番批判されないに決まっているじゃないですか、ある意味では。でも凄くカッコいいものというのは大体それに成功しているものなんじゃないかなと思うんですよね。それに失敗したもの、世の批判を集めてしまったものが価値がないかと言うとむしろ逆で、それは将来の価値になるかもしれないものだったりするわけです。ダーウィンの「進化論」なんて批判されてそれを繰り返して4回くらい改変されていますけど、そういうものなんじゃないかと思うんですよね。しかもこんなに世の中がわかりにくく、将来のことが読めず、不安な時代はないと思うんですね。でも一方で、こんなに豊かな時代もない。これだけ豊かで余裕がある状況なのに、それでもエッジで果たしてダンスを踊らないんですか? と僕は思うところなんです。だっていまこそ色んなものをディスラプトしなければいけないわけですよね。色んなものが再定義されているのだとしたら、色んな人がトライしないといけないはずなのに、いままでものじゃないからという理由で同じことをずっと続けていてもまともに革新されないだろうし、可能性があったとしても間に合わないですよね。それは嫌だなと思うんです。
原田:お話を聞いていて思ったのは、太刀川さんが最初に話されていた原体験ではないですが、「色んな領域で実はデザインが求められているんだ」ということに味をしめるというか、そういう体験ができるとどんどんそっちに行くということがあり得ると思うんですよね。
太刀川:本当にそれだと思います。最近、地域のデザイナーがメチャクチャ面白いじゃないですか。あれはデマンドがわかりやすいからだと思うんです。「え、そんなことやっていいすか?」みたいな。おっちゃんたちも「何をやってるのかわからないから君たちに任せるよ」みたいなことが地域だと起こっているんですよね。そういうことが大企業でも起こればいいですよね。
原田:今日は「越境」をテーマに、デザイン領域の中での越境と、デザインを離れたところでのさまざまな専門家との協働という意味での越境の話を伺いました。次回は、太刀川さんが提唱されている創造的思考法『進化思考』のベースになっている自然に学ぶ創造性やデザインのあり方をテーマにお話を聞いていきたいと思っています。今日もありがとうございました。
太刀川:ありがとうございました。
最後までお読み頂きありがとうございました。
「デザインの手前」は、Apple Podcast、Spotifyをはじめ各種プラットフォームで配信中。ぜひ番組の登録をお願いします。
Apple Podcast
https://apple.co/3U5Eexi
Spotify
https://spoti.fi/3TB3lpW
各種SNSでも情報を発信しています。こちらもぜひフォローをお願いします。
Instagram
https://www.instagram.com/design_no_temae/
X
https://twitter.com/design_no_temae
note
https://note.com/design_no_temae