既存の関係を“不可視”化するケアのデザイン | 金野千恵さん〈4/4〉
「デザインの手前」は、デザインに関わる編集者2人がさまざまなクリエイターをお招きし、デザインの本質的な価値やこれからの可能性についてお話しするトークプログラムです。ニュースレターでは、最新エピソードの内容をテキスト化してお届けしています。建築家の金野千恵さんをお迎えする最終回は、改めて「デザインとケア」という観点から、金野さんの建築が持つ価値や意義についてお話をしました。
なぜいま「ケア」なのか?
原田:今日は直球のテーマになりますが、「デザインとケア」という切り口で色々お話をしていきたいと思っています。
最近デザインの世界においても「ケア」という考え方が重視されていて、それは医療や介護、福祉などいわゆる狭義の「ケア」だけではありません。これまでのデザインはマジョリティに向けたマスコミュニケーション、マスプロダクションというところが中心でしたが、そこから除外されてしまっていたマイノリティの人たちに向けたデザインというものも注目されてきています。
例えば、障がいのある方や外国人、高齢者などをデザインのプロセスに巻き込むインクルーシブデザインというものがあったり、Webデザインの世界においてもアクセシビリティを重視したサイトの設計がされるなど、デザイン全般においてケアという考え方が注目されています。特に象徴的なのは、近年のグッドデザイン賞で大賞を受賞している作品のほとんどがケアに関わるもので、むしろ偏り過ぎていると感じるほどです(笑)。

原田:金野さんご自身もケアという文脈から注目されることも多いと思うのですが、金野さんがつくる建築は「春日台センターセンター」など複数の用途を持っているものが多く、その結果色々な人たちが集まってきます。社会福祉士がコロッケを売るというのは、そうした金野さんの建築を象徴する光景ですよね。それを見ていて思うのは、金野さんがつくる場にはその人がもともと持っていた役割を一度解除し、新しい役割を与えていくようなところがあるということです。
ケアする/されるの関係をいかに外していくのかというのは、ケアの問題を考える時に重要だと思うのですが、そうした既存の力関係や役割を一度見えなくしてしまうところが面白いと言うか、大事なところだと思っています。
デザインというのは物事を可視化するものだという考え方があって、例えば原研哉さんは「本質を見極め可視化をする」ことがデザインであると仰っていて、それはひとつの真理だと思うんですね。一方で、既存の力関係を強化してしまうところにデザインが寄与してしまうこともあって、そうしたデザインの暴力性みたいなものにも目が向け始められている気がするんですね。そうした中で、関係を「不可視化」するようなデザインのあり方というのが、ケアを考える時に重要な観点のひとつだと思っていて、まさに金野さんはそういうデザインをされている印象があり、今日はその辺のお話ができたらと考えていました。
山田:金野さんのお仕事で「ミノワ座ガーデン」という特別養護老人ホームがありますよね。老人ホームというのは街の中にあっても意外と見えてこない場所です。いまの「可視/不可視」の話で言うと、ちょっと逆転現象が起きているのかなとも思うのですが、このプロジェクトでは柵やコンクリートの塀を取り払って、かなり大胆にオープンにしていますよね。それによって、そこに暮らされている方々と街をつないでいるところがある。また、僕たち自身もいずれその世代になっていくわけですが、老人ホームという存在をあまり認識できていないところもあります。そういうものを目に見える形にしているという点で、凄く意味がある仕事だと思っているんですね。

金野:実は、「なかなか大変そうなホームだな」というのが第一印象でした。高さ1.4メートルの塀が80メートルくらい続いているのですが、施設の入居者のほとんどが車椅子だったこともあって、私も実際に車椅子に乗って進んでみたんです。そうすると塀で中が全く見えなくて、塀が途切れたと思うと鉄扉がガラガラと開いて、「あ、ここに入っていくのか」と。こうした施設然としたところはどうやってアプローチしたらいいんだろうと思ったのですが、運営者の方は凄く先を見ていらしていて。いま地域とつながっておかないと今後どんどん苦しくなっていくし、介護の担い手も少なくなってしまうという状況の中で、先ほど仰っていただいたケアする/されるという関係や、街から見えるイメージを変えていかないと苦しいと感じられていたんですね。
実際に施設の中に入ってみると、利用者さんもスタッフさんも凄く穏やかな顔をしていて楽しそうですし、「なぜわざわざ見えなくしないといけないんだろう?」というのがまずはかなり疑問だったんです。そういう意味である種の「可視化」でもあるのですが、同時に敷地を分けてそれぞれが所有するという近代的な概念である「境界」というものをいかに「不可視化」すると言うのか、なかったことにしたらどうなるのかということでもあったんです。
歩道なども含めてこの辺りをみんなが使えるようにするには、見せるにはどうしたらいいかということを考えていったプロセスでした。この時は「庭」を求められていたので、建築的に何ができるのだろうというのはあったのですが、居場所として成立させていくために影をどうつくっていくのかとか、「ミノワ座ガーデン」という名前の通り、とにかく座れる場所をつくっていけば、施設の方々が出てくることに加えて、町の人たちも使ってくれるはずということを考えながら進めていきました。
それまで塀の中を通っていく人はいなかったのですが、いざ塀を取ってみるとここを行き来する人たちがわざわざ通っていったり、業者さんも庭を通ってエントランスに入っていくというこれまでと全然違う流れができていきました。まさに「活動の可視化」と「境界の不可視化」をしていくことで、日常の風景の見え方が全然変わったなと思います。
↓こちらからポッドキャスト本編をお聴きいただけます
▼Apple Podcast
▼Spotify
↓続きもテキストで読む
境界をなくすことで生まれる役割
山田:ベンチなど座る場所が都市の中にないという話が前回ありましたが、金野さんの建築には座る場所がたくさんありますよね(笑)。そうするとみんな必然的にそこに座るし、それは自分の場所をつくっていくということなんですよね。「ミノワ座ガーデン」はまさにそういう意味で人が集える場をある意味取り戻したということですよね。近代/現代における「領域」という凄く資本主義的な話から、もっと民主的な場に変わっていった好例だと思うんですよね。そういう意味では僕たちにとっても凄く恩恵のあるケアなのかなという気がしました。
金野:そうですね。この庭ができたことで、通りがかりの人もそうですし、犬を連れて散歩していた方がここをコースにするようになったり、園庭を持たない近くの保育園の園児たちが毎日遊びに来るようになりました。そうやって開かれていて、「使っていいよ」と許されているように見える場所は、みんなが使い方を発見していくようなところがあって。本来そういう能力がみんなにないわけではなくて、機会が奪わてしまっている状況なんだよなというのは、改めてこういう空間をつくって色んな人が色んな形で使ってくれている状況を見ると凄く感じますね。
原田:境界をなくしていくという話がありましたが、それによって初めて新しい役割や居場所が見出されていくというのは凄く面白いと思っています。デザインというのはどちらかというと「整理」をするものだという考え方が主流だったと思うのですが、色々なものを整理してきたがゆえにセグメントされ過ぎてしまったところがありますよね。山田さんも以前のエピソードで話していた「春日台センターセンター」のように、さまざまな人がモザイク状に混ざる建築というのは、効率を考えるともっと整理をした方がオペレーションがしやすくなるという話になると思うんですね。でも、あえてその整理をせずに、バラバラなものをバラバラなまま扱うような場のつくり方をされていますよね。
それによって既存の役割や肩書き、関係性というものが取り外され、新しい自分の役割が見出されていくようなところがあるのかなと思っていて、それが社会福祉士がコロッケを売るというところにつながってくるのかなと。
建築家やデザイナーも専門家としての肩書きを持っていますが、例えば、「春日台センターセンター」のワークショップの時に、金野さんが毎回新聞をつくっていたという話も、まさに専門家としての肩書きを一度外したからこそできた振る舞いだったかもしれないですよね。建築の専門家と福祉の専門家がコラボレーションするという時にも、一度肩書きを外すということが必要だったのかもかもしれません。金野さんの活動には、そうやって色んなものを一度キャンセルしていくということがさまざまなレイヤーで見られますよね。
金野:そうですね。最初にお話し頂いたように、私たちがいま関わっている仕事は本当に色んな方が交わっていくような空間が多いんですね。でも、例えば福祉の施設の場合、いくつもいくつもサービスがあるほど設計も大変だったりするし、事業者の方も凄く大変なんですね。
少人数のものがたくさんがあると、一つひとつ制度が違うので窓口やお金の支出もそれぞれ異なるし、事務的に見ると手間が増えるだけで良いことはないんです。建築的にも、子どもの居場所と高齢者の居場所が併設すると用途が異なるとみなされ、異種用途区画というものになるんです。建築的に複雑に解いていかないといけないような制度ができてしまっている部分があって、組み合わせれば組み合わせるほど大変になるのが現状なんですよね。やってみるとそういうことがよくわかるのですが、何かしら突破口だったり、これとこれはダメだけどこの間はグレーで明確にダメだとは書かれていない領域が見えてきた時こそ、クリエイティビティが凄く発揮されるところだと思っていて。
こうするのはダメじゃないからやってみようと思ってやってみると、案外できるということが結構多いんです。特に「春日台センターセンター」は本当に複雑に入り組んでいるのですが、制度上は割とシンプルに見せていて、使い手からすると制度の線がどこにあるのかはほとんどわからないまま、それぞれが居心地の良い場所を選びながら使っている。時には空気を読みながら、「そこでおばあちゃんが寝ているからこっちに行ったほうがいいかな」という関係性でみんなが使いこなしていくということができるんだという確信を得ることができました。実際にやってみるとできるクリエイティブゾーンというのは案外広いことが見えてきたし、福祉のサービスも建築の制度も一生絶対のものではないと思っていて、規模によってはその分節がおかしなことになっているということを発信をし続けることで、変わっていく未来もあるのだろうなと。
「ケア」と「仕組み」を行き来する
原田:金野さんの事務所の名前は「t e c o」ですが、小さな力で大きなものを動かすテコのように、仕組みから考えていきたいという旨のテキストが書かれていますよね。
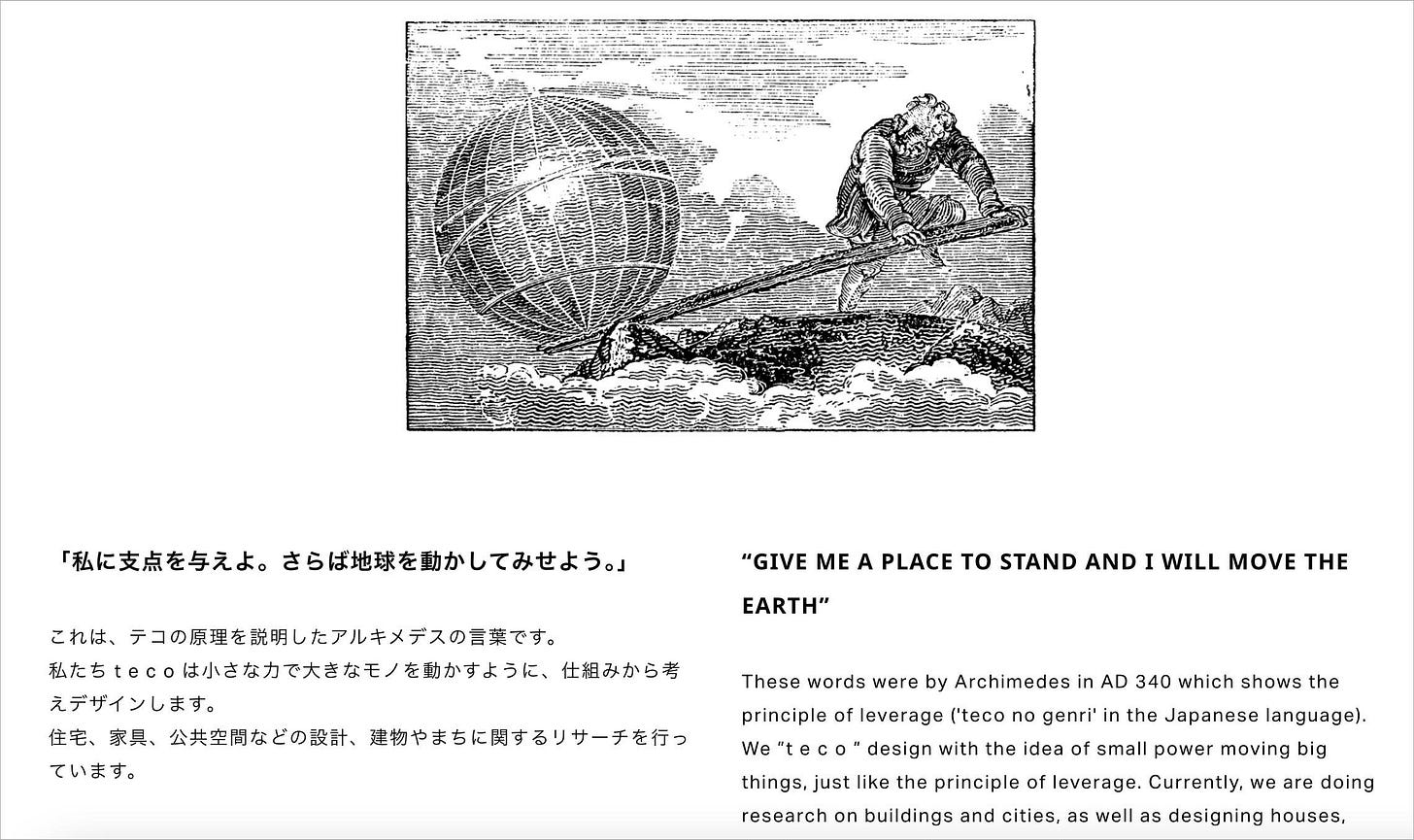
原田:「仕組み」というのは「制度」よりはもう少し緩やかなものであり、「ケア」ともまた違うものですよね。前回「デザインの手前」にご出演頂いたオンラインメディア「designing」の記事で、デザイン研究者の上平崇仁さんが、デザインには「仕組みのデザイン」と「ケアのデザイン」があるということを仰っていたんですね。前者が、複製できる大量生産のためのプロのデザインであることに対して、ケアを前提としたデザインというものはもう少し生活者に寄り添うもので、この2つのデザインを行き来していくことが大切だと。まさにテコという仕組みを会社名にしている金野さんは、こうした「ケア」と「仕組み」の関係についてどのように捉えているのかなと。
金野:たしかに仕組みづくりには凄く興味があります。仕組みというのは仰るように制度みたいなものとはちょっと違うもので、それが上手く回っていくための自分たちなりの方法論というか、そういうものも含めて考えているのかなと。
最初のエピソードの話とも連動させるなら、インドネシアにある「バレ・バンジャール」という空間では、まさに「ケア」と「仕組み」が両方しっかり組み立てられた環境が生まれているんですね。「バンジャール」というのがコモンズの単位といった感じで、300人から500人くらいまでとサイズにはバラツキがあるのですが、そういう人たちが覆いの下で、自分たちの共同体の中で次に何をケアしていくべきなのかという議論をしていて、例えば子供が増えてきたから自分たちで保育園をつくるとか、それをどういう風に成り立たせていくのかという仕組みもみんなで一緒につくっていくんです。あるいは高齢者が増えたから、違う場所に共同体として土地を持って、穏やかに暮らせる場所を自分たちでつくっていこうとか、それぞれが暮らしやすい環境をつくっていくために、仕組みづくりも一緒にやっていくというのが凄く連動していて。バレ・バンジャールは調べ始めてから2年目くらいなのですが、そもそもケアというのはボランティアとか優しさということだけでは成り立たなくて、それを成立させるためにはお金をどうやって得ていくのかとか、継続的に誰かが形づくっていくにはどういう組織体が必要なのかみたいなことを行ったり来たりすることで継続していく環境というのがあるのかなと思っていて。その辺りの仕組みから考えると、環境にどういうものが適しているのかという本質に迫れるのかなと感じています。
原田:「ケア」はどちらかというと、目の前の相手とどうコミュニケーションをしていくのかという意味で「一回性」のイメージがありますが、結局それを上手く回していくためには「仕組み」が必要で、「ケア」から始まって「仕組み」に行き着くという感じですよね。多分そのどちらかだけがあってもダメなんでしょうね。
建築やデザインが人をつなぐ
山田:金野さんの発注主は企業や個人だと思いますが、もうちょっと共同体となってきた時にそことどう向き合うか。事業母体として金野さんのクライアントは明快に立っていると思うけれど、「バレ・バンジャール」というのはもう少し共同体にあたる部分なのかなと。建築というのは本当はもう少しそこに関与できる可能性があるというか、それがケアにつながっていくということですよね。
金野:おそらく、最先端のケアの事業者たちが切実に感じていることだと思うのですが、サービスをする/されるという関係性を保とうとするともう崩壊し始めていて。自分たちだけがギブという形を取っていく時代ではなくなった時に、もう少しみんなで一緒に肩を並べて考えていくような関係性をつくっていく、それが多分コモンズみたいなものだと思うのですが、そういう環境をつくっていくのはいまの制度ではなかなか難しくて。そういう制度を乗り越えた環境をつくっておくにはどうしたらいいかという時に建築やデザインというものが役に立って、色んな人を繋げていくとか、関心を持ってもらうとか、日常的な居場所にしてもらうということができる。そうやってデザインだったり、居場所みたいなもので繋がれていった人たちが新しいコモンズみたいなものをつくっていけると、いざという時には国や制度に頼らなくてもある程度自活したり回っていく仕組みがつくれるし、並走してすでに動いているものがあるという形にしていくことが多分彼らの理想なんだろうなと。だから、やっぱり目の前の課題を解くことだけが私たちの仕事ではないというか、もう少し長い目で見て、どういう環境づくりがいま必要なのかということが大事なところかなと思います。
原田:ここまで4回にわたって金野さんに色々お話を伺ってきました。いまも色々なプロジェクトが動いていると思いますが、長期化しているというお話もあったので、近々で見られるものとしては、やはりロッジアの書籍ということになるんですかね。
金野:そうですね。あとは、都内で小さな建物なんかも今年できたりしますし、実は万博にも関係していたりするので、そういうものも着々と動きながら、という感じですね。
最後までお読み頂きありがとうございました。
「デザインの手前」は、Apple Podcast、Spotifyをはじめ各種プラットフォームで配信中。ぜひ番組の登録をお願いします。
Apple Podcast
https://apple.co/3U5Eexi
Spotify
https://spoti.fi/3TB3lpW
各種SNSでも情報を発信しています。こちらもぜひフォローをお願いします。
Instagram
https://www.instagram.com/design_no_temae/
X
https://twitter.com/design_no_temae
note
https://note.com/design_no_temae





