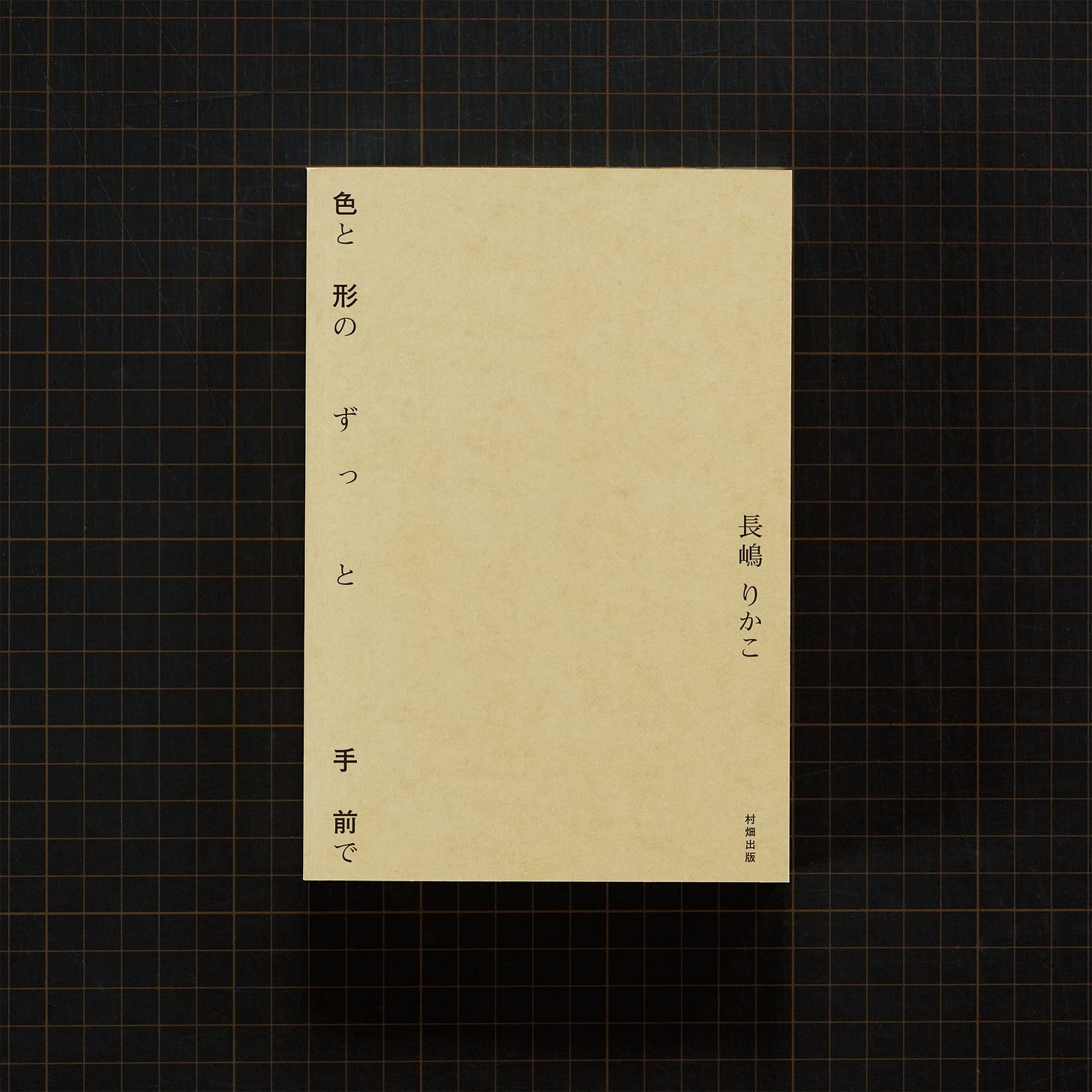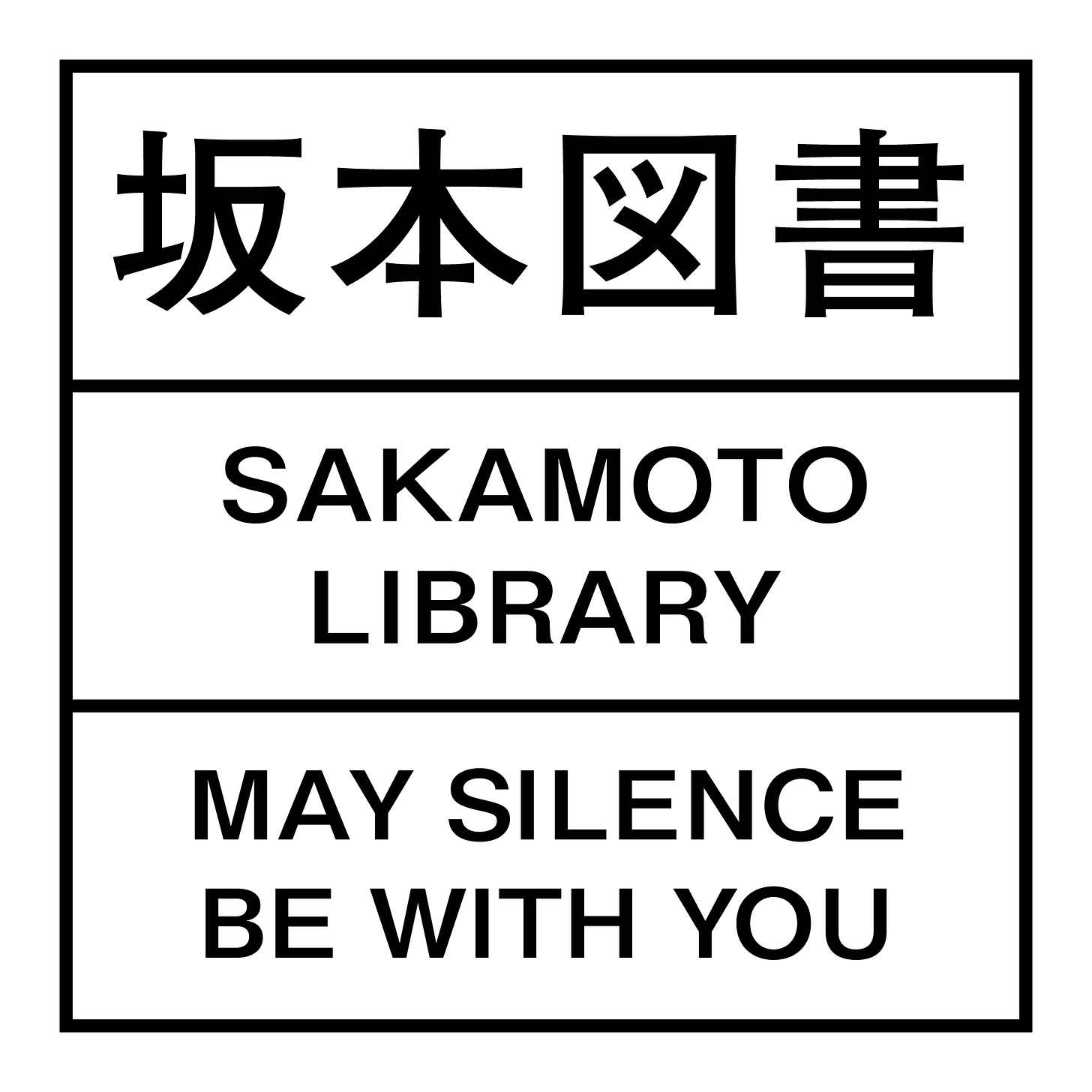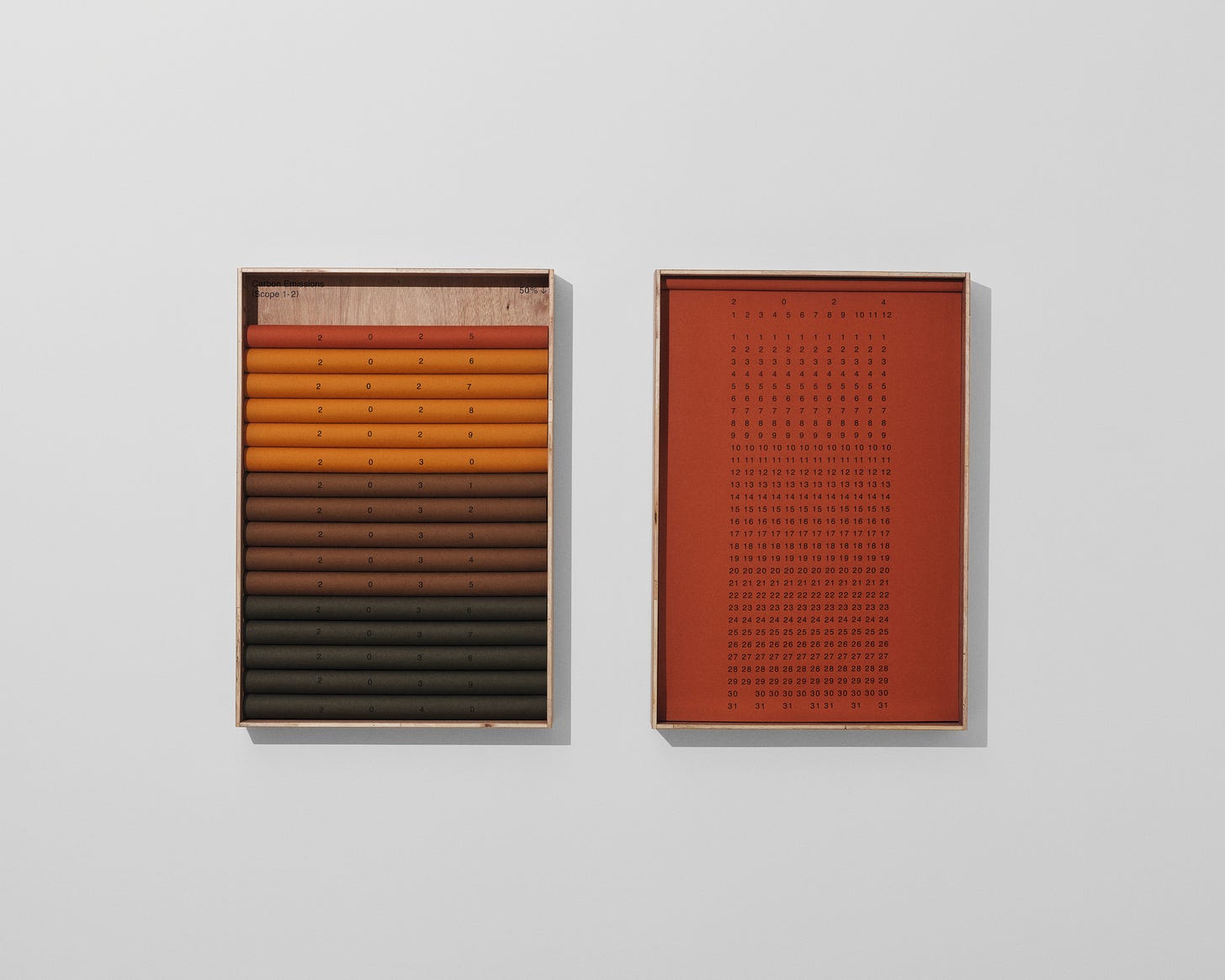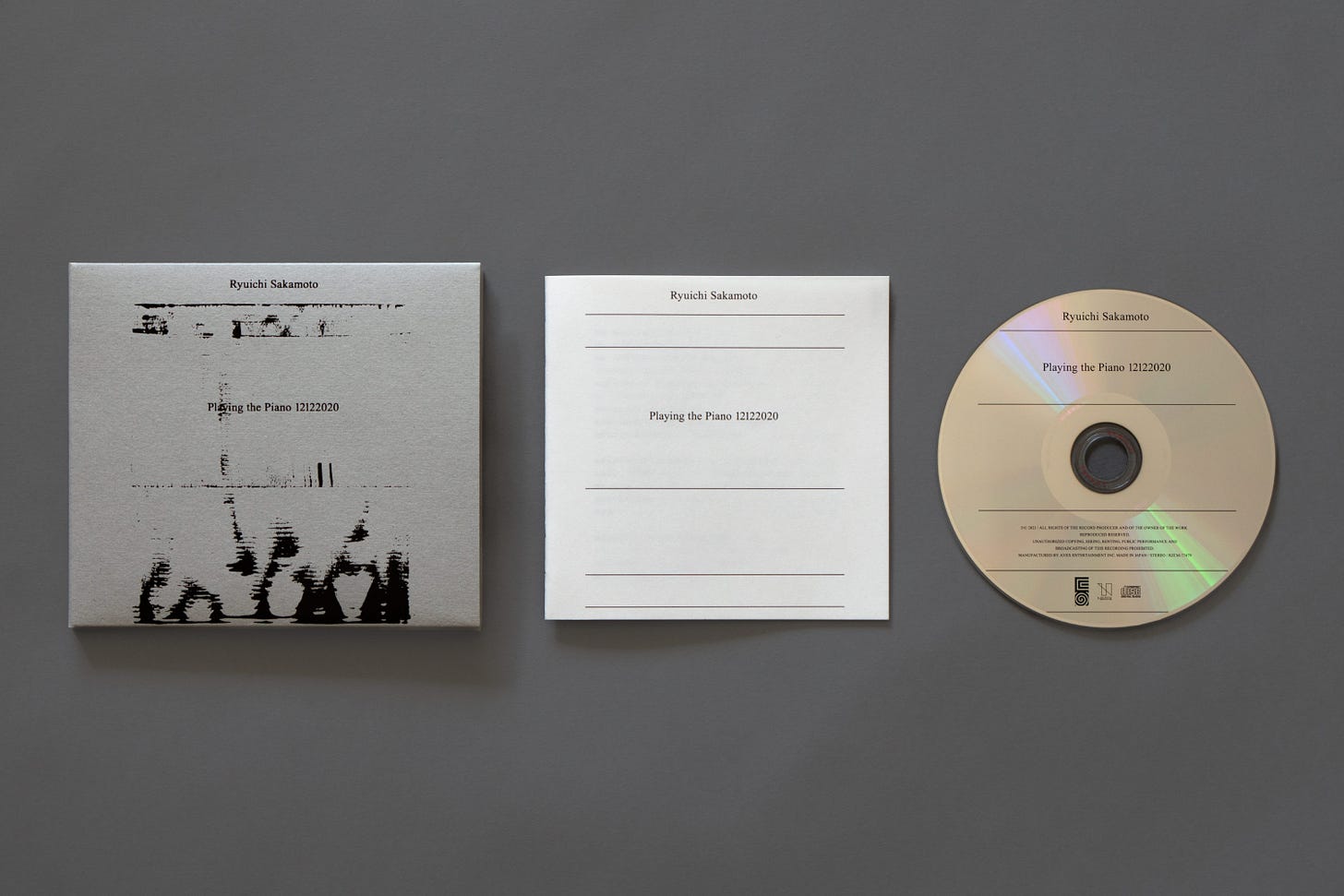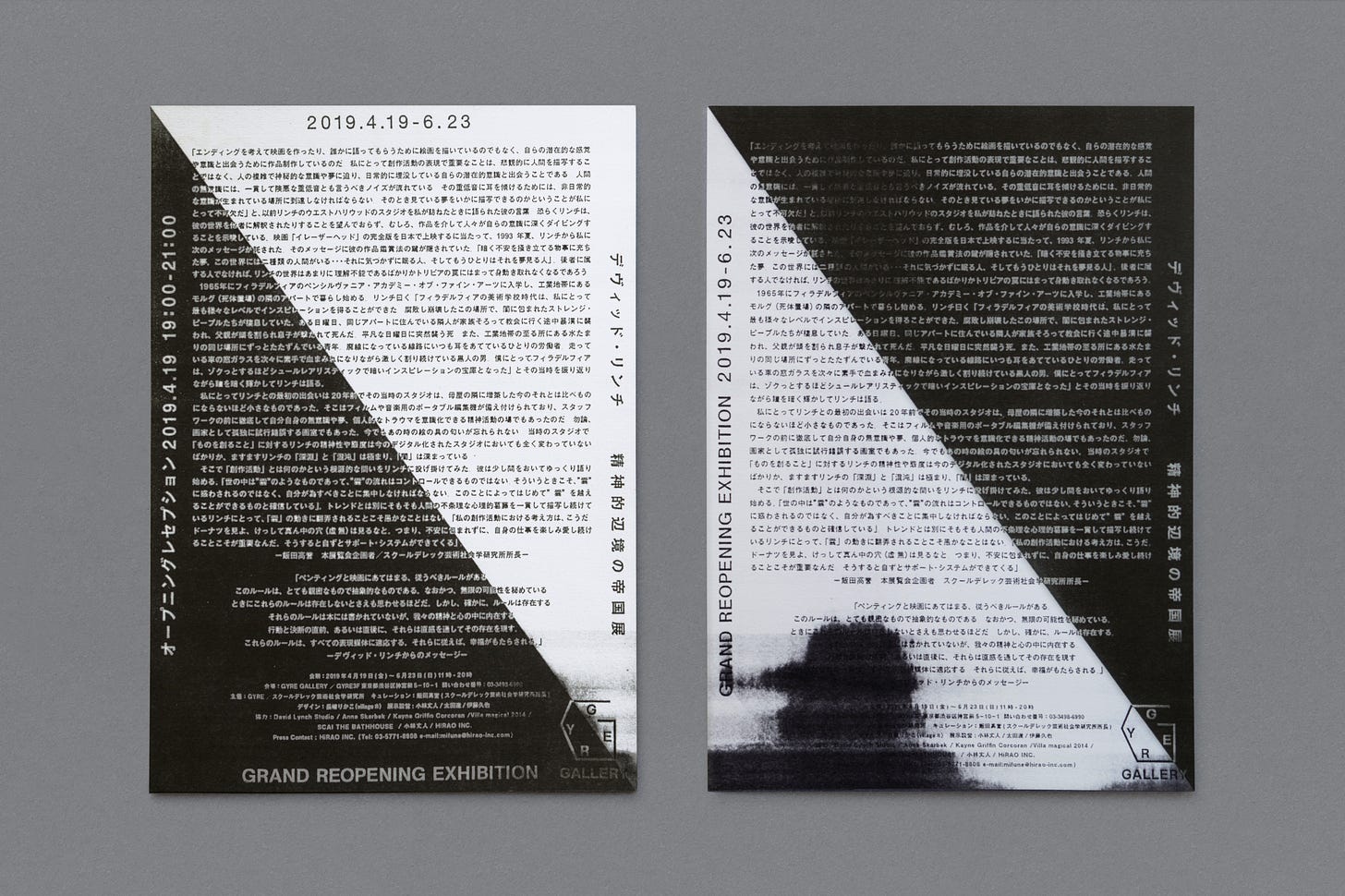エンブレム問題が教えてくれた、言葉を発することの大切さ | 長嶋りかこさん〈3/4〉
「デザインの手前」は、デザインに関わる編集者2人が、さまざまなクリエイターをお招きし、デザインの本質的な価値や可能性についてお話しするトークプログラムです。ニュースレターでは、最新エピソードの内容をテキスト化してお届けしています。グラフィックデザイナー・長嶋りかこさんによる3回目のエピソードでは、「デザイナーが言葉を持つこと」というテーマのもと、デザイナーと社会の関係などについて話し合いました。
どう伝えるか? / 何を伝えるか?
原田:今日は「デザインと言葉」というテーマでお話をしてみたいと思います。長嶋さんは、デザイナーとしてこの本を言葉で表現したという話が前回ありましたが、グラフィックデザイナーをはじめデザインに関わる方たちとお話をしていると、言葉が苦手だからデザインをしているという人が結構多いんですよね。本にも書かれていましたが、長嶋さんももともとはそういうタイプだったそうですね。
長嶋:はい、小学生の頃は全然言葉を発しない子どもでした。喋るようになったのは絵を描くようになってからなんですけど、いまもプレゼンは大嫌いだし、昔から人前で何かをするのが苦手で。だから、視覚言語というものを知った時に「これだったら喋らなくて済む。絵が伝えてくれるから喋らなくていいじゃん」と(笑)。この技術が自分をその先に繋ぐ気がすると思ってどんどん興味を持ってやっていったというのはありました。「何を伝えるか」ということよりも「どうやって伝えるか」というところに興味があった時期が凄く長かったんですよね。
でも、そこからやっぱり「何を伝えるか」ということは隅に置いておけない話なんだなと思うようになっていくのですが、それは広告代理店での経験が結構大きくて。というのも、当時は「何を伝えるのか」という中身に対して責任を持ち切れなかったんですよね。それはどの仕事を選ぶのかみたいなこともあるのですが、やっぱり大きな組織なのでチームングも含めて自分だけで判断できる座組になっていないところがあって、関わる商品や活動という「内側」に対して自分が本当に良いと思ってなくても、「外側」をつくらなきゃいけない状況が結構ありました。実際にデザインしたものが世の中に出ると、友達は「りかこがデザインしたなら買うよ」と言ってくれるのですが、「ごめん、本当に中身が美味しくないから買わなくていい」とか言ってしまい(笑)、私何やってんだろうと。デザインの仕事をしたいと思って広告代理店で仕事をしているのに、そこでつくっているものを自分は友達に紹介すらできない。こんなに朝までがんばってやってきた仕事なのに、友達や家族におすすめできないって、本当何やってんだろうと悲しくなってしまって。「どう伝えるか」の手前の「何を伝えるか」ということは凄く大事なんだなというのは、代理店時代の苦い経験として自分の中の肝になっている部分があります。
原田:果たして世のデザイナーのどのくらいの人がそういう違和感を持てているんでしょうか。これは仕事のスタンスかもしれないですが、割り切ってやることも全然できるし、必ずしもそれが悪ではないと思います。その捉え方やスタンスはやっぱり人それぞれなんだろうという気はしますよね。
長嶋:そうですね。私はその違和感が凄く強かったんですよね。それはやっぱり自分の生い立ちとも関係していると思うんですけど、こんなにモノを薦めて売って、こんなに消費させて、でも「すぐゴミになるじゃん」と考えると、「だったらつくらない方がマシかも」と思ってしまったり。単純に色と形が綺麗であったり、雰囲気を持って何かを誘導していることがなんか罪だなと思ったりする部分が強かったんですよね。もちろん悪い面だけではないんだけど、良い面だけじゃないということを感じるようになってきて。だから、素敵なデザインなのに中身を見たら何もないみたいなものにも触れたりすると、「何のためにデザインってあるんだっけ?」って思うようになってしまって。
↓こちらからポッドキャスト本編をお聴きいただけます
▼Apple Podcast
▼Spotify
↓続きもテキストで読む
なぜデザイナーの言葉は少ないのか?
原田:色と形をつくれていれば喋らなくてもいいというところに寄りかかってきたデザイナーたちは、もっと自分がつくるものを言語化しなさいと言われることがよくあると思うんですね。コンセプトを言語化するとか、それこそ長嶋さんが苦手だったプレゼンテーションをしっかりやる能力をつけるとか、「デザイナーと言語」というテーマだとそういう話になりがちです。でも、つくっているものをちゃんと言葉にしなさいという話と、長嶋さんが発している言葉はだいぶ違うというか。例えば、デザイナーが本を書く場合も、デザインのメソッドやノウハウを多くの人に伝えるというケースが多く、そうした言語化の力がある方はたくさんいると思うのですが、長嶋さんがされている言語化は全然レイヤーが違う言葉の育て方だったり、プロセスなのかなと。そこの言語をちゃんと持てている人はやっぱり少ないのかなという気はします。
山田:特にグラフィックデザイナーはあまり言葉を発してこなかったのかなと。建築家は放っておいても自分から喋るんですけど(笑)。グラフィック界には錚々たるデザイナーがいますが、そういう方たちの自伝はあまりないし、そもそも言葉が残されていない。田中一光さんとかも作品集はたくさんあるけれど、一光さん自身の言葉や文章はあまり残されてなくて、そこにどんな思考があったのかというところはあまりわからない部分ではありますよね。
長嶋:『暮しの手帖』をつくった花森安治さんは、実際彼がどれだけ言葉を残したのかはわかりませんが、「なぜそれをやったのか?」ということが明確にある人ですよね。デザインをする時に、その先に社会があるということをどれだけ意識していたのかというところでは、花森さんにはそれが確実にあったと思います。
山田:そうですね。1960年に世界デザイン会議があった時は、みなさん積極的に発言されていて、田中一光さんに関しては日本の美や伝統色みたいなことに対しての言葉は結構見えるのですが、一光さんが生きた時代の社会とか、その中で何を考えてそこに至ったのかということが、もしかしたら凄く私的なことだからみんなあまりそこは語らなかったところもあるのかなと。
原田:その先に社会があるのかということを長嶋さんが仰いましたが、社会とのつながりをどこまで想像できているのかということが凄く大きい気はします。それで言うと、いまはより社会につながっていかなければいけない時代だからこそ、伝える「手法」としてのデザインというだけではなく、「何」「なぜ」というところをデザイナーがしっかり語っていくことはどんどん大事になってきているはずです。
先ほど山田さんから「世界デザイン会議」の話がありましたが、世界デザイン会議はたしか運営が2つあって、ちょっとどちらか忘れてしまいましたが、昨年も東京で世界デザイン会議があったんですよね。それを見ていても思うことは、世界の人たちが集まってデザインのことを語る場に、デザイナーがあまりいないという不思議な状況が起きているということです。デザインの研究者やソーシャルビジネスをされている方などがデザインについて語っていて、社会的にデザインがより大切になっている時代なのに、その当事者としてのデザイナーが社会との接続をちゃんと言葉にできないということがあると思っていて。長嶋さんが言うところの「違和感」をちゃんと発しようとすることによって言葉が育てられていくような気もするんですけど、違和感とちゃんと向き合うということを、それこそ前回の長嶋さんのお話のように、蓋をしすぎてしまっているのかなと感じるところはあります。
長嶋:あともしかしたら、気にならなくていい世界を生きてるのかもしれませんね。逆に言うと、私が気になってしまう世界を生きていたというのはあるかもしれない。貧乏な家で育ったということもそうだし、デザインというものが凄く特権的な界隈にあるものなんだなということを大学に入ってもちょっと感じたんですよね。同級生たちも裕福な人が多いなとか(笑)。社会というものを意識しなくても悠々自適と言っていいかわからないですが、それ故に色と形を穏やかにつくれたのかなという気持ちもちょっとあります。
言葉が響き合う状況をつくる
山田:長嶋さんの本のあとがきに、グラフィックデザイナーの福岡南央子さんの名前が挙がっていますが、謝辞に出てくるのはどんな経緯があったのですか?
長嶋:「表現と政治」という活動をしている女性たちがいて、惣田紗希さんというイラストレーター兼デザイナーの方と、平山みな美さんというデンマーク在住で、環境活動家をしながらグラフィックデザインをしている方と、編集者の岡あゆみさんという方の3人で活動されていて。社会と接点を持ちながら、何かデザイナーができることはないだろうかと考えながら活動していると思うんですけど、彼女たちが不定期でやっている「表現と政治」というオンライン配信のトークイベントに、私と福岡さんがゲストとして呼ばれて、みんなで対話をしたことがあったんですよね。その時は題材がジェンダーだったんですけど、福岡さんがそういう活動にかなりコミットしているということをその時初めて解像度高めに知ることができたんですよね。彼女が色々話してくれたこともそうだし、この会自体が(平山)みな美ちゃんたちによって開かれたということも私の中では結構大きくて。あの場で話した内容はもちろんだけど、オンライン参加してくれた人たちのコメントや感想とかも後で見ることができて、そこには結構切実なものがあったりして、やっぱりみんな感じている違和感があるんだなと。福岡さんも、「表現と政治」のメンバーも、聞きに来てくれた人たちも含めて、みんなから聴いた声が自分の中では結構大きくて。やっぱり自分がいま感じている違和感を社会に届ける必要があるだろうなと思えたんですよね。それで謝辞に書いたというのがありました。
山田:やっぱり声を発している人たちはちゃんといるということなんですね。
長嶋:そう。届け方はさまざまだし、時に声は小さかったりもするけど、自分はできれば少しでも長く続く声にしたいなというのがあって。この本も出して終わりじゃなくて、実際やっぱりリアクションも凄くあるから、ほんの少しでも世の中の変化につながればいいという気持ちがあるし、できる限り長く続く声にしたい。女性は共感の声が多くて、「言葉にしてくれてありがとう」みたいな感じでした。
山田:ちなみに男性の反応はどんな感じでしたか?
長嶋:男性からもかなり来るんですよ。例えば、とある建築家の男性は、自分の事務所のあり方を考えると言ってくれたり、子育てをしていく中で自分がどれだけパートナーに負担をかけているのかということも省みたりしてくれて。自分の過去を振り返りつつ、これからどうするかというところにつなげて考えてくれる意見が男の人は結構多くて、それは本当に心強いなと。私が書いたことに対して、「うるせーよ」じゃなくて(笑)、そうやって考えて何らかの変化に繋げようとしてくれていることはうれしいなと思っています。
山田:そうやって言葉が響き合ってどんどん広がると、他の人ももっと言葉を発しやすくなりますよね。これは仕事というか人生のあり方の本だから、こういうことをもっと言っていいんだとか、そういう広がりが得られると、言葉を自分から発していくようになる。今回みたいに自分で出版社をつくってそこから出されることの意味は凄く大きいなと。
長嶋:漆作家の方で長野で活動されている方がいて、彼は作家活動を続けながら料理や家事などほとんどのことをやっているんですよね。彼女の方は比較的お仕事に集中しているのですが、お互いの納得の上でそういう体制を選んでいる人がいるように、子育てにおけるパートナーシップの形にはかなり色んなバージョンがある。その中には必ず創作を続けるための工夫があって、そこにはいままでなかった「親」像がきっとあると思うから、そういうものをケースとして見せていく、伝えるみたいなことがあればいいなと思って、その漆作家の方なんかは取材したいと思ったんですよ。
山田:たしかに長嶋さんがインタビューをして回って、働き方とか家族とか自分の暮らしをつくりながら、仕事をどうやっていくのかというところはみんなにもっと伝えていきたいですよね。
いまのお話は凄く示唆的だと思うのですが、男性は社会に出なきゃいけないみたいな強迫観念があって、でも必ずしも社会に向いている人ばかりではないから、家庭の中で自分のペースで仕事をして、例えばパートナーの女性がもっと社会に出ていきたい人だったら、彼女がそちらの立場に立って、家のことは男性がやったり、色んな選択肢があって然るべきだし、それは関係性の中で決めていくことですよね。その選択肢がもっと自由でいいんだということを社会そのものが認識していくべきだし、それは許容とかでもなんでもなくて、そういうものなんだという認識をもっと持たないといけないですよね。
長嶋:家族の形も同じかなと思っていて。片親もそうだし、2人親もそうだし、もしかしたら養子ということもあるかもしれない。そういう環境に身を置きながらものづくりをしている人の話をもっと共有できたら色々変わる気がします。
大きな学びとなったエンブレム問題
原田:メディアに関わる人間としても、そういった声をちゃんと拾う、ケースを伝える機会をつくっていくことは凄く大事なことだし、これはデザイナーに限る話ではないと思いますが、当事者として違和感や葛藤をちゃんと言葉にしていくということがもう少し習慣化されていくといいですよね。それによって言葉が言葉を呼ぶといった状況もできるだろうし、デザイナーに関して言うと、そういった日々の習慣がもう少し広がっていくことで、本当に社会に言葉を発しなきゃいけない時の言葉も変わってくるのかなと。もしかしたら、東京五輪のエンブレムの話もそうかもしれないし、そういう意味でコンセプトの言語化とかとはぜんぜん違う、言葉にしていく行為というのは色んな職種で大事だけど、特に社会とコミュニケーションを取っていくデザイナーにとってHOWの部分だけではない言葉を持つことがとても大事なことだなと思いました。
長嶋:本当にそう思います。エンブレム問題は私にとって本当に辛いことでしたが、そこから凄く学びがありました。当時の自分を振り返ってみるとやっぱりちょっと下駄を履いていた部分があったから、権威だの名誉だのそういうものが全部なくなったことは逆に良かったなと感じています。自分から脱いだ感じだったんですけど。
原田:デザイン界自体はそこから大きくは変わっていないような気もしますよね。
長嶋:やっぱり私自身が失望したということがあって。やっぱりデザイナーが欲しくて手に入れた権威でもあると思うんですよね。過去の巨匠たちが図案家と呼ばれていた時代から、自分がデザイナーであることを名乗って、それを社会に確立していくために権威化していく行為は必要だったのかもしれないけど、結局いま何が残っているんだろうと。色々なデザイン団体があるけど、やっぱり権威だけがあって空洞化しちゃっているみたいなことはあるんじゃないかなというのは思っていて。それが如実に出たのがエンブレム問題だったのかなと思うし、やっぱりああいうことが起きた時に当事者である私が声を発せなかったというのはもちろん後悔としてあるし、それは私の至らなさでもあるという大前提があるんだけど、同時に各団体がどういう考えや指針を言葉で出すのかという時に、結局何も出て来なかったことがやっぱり自分の中では大きかった。もちろん、小さなスケールで「この問題は一体何なのだ」と言葉にしようと試みていたデザイナーの人たちもいたけど、やっぱり多くはそうではなかった。結局、デザインは何のためにあるんだっけ? という話に戻るのですが、社会に接続しているはずのデザインなのに、色んなレイヤーがある社会の中で、結局一番上の層しか見ていなかったんだなという感じがして。本当にたくさんのレイヤーがあって、色んな声や背景の人たちがいるんだけど、その状況をデザイン業界もデザイナーも直視していなくて、やっぱり利権があるところで仕事が成り立っていて、(デザインが)経済とともにありすぎたことがこういう結果を招いたんじゃないかと。
長嶋:自分個人の話で言うと、私自身オリンピックの開催に対して反対の気持ちがあったんですよね。やっぱり東北の復興がままなっていないのにお金を五輪に投下することが果たしてどうなんだろうと。そういう気持ちがあるのに、審査を依頼された時に受けてしまったということ自体にまずそもそもの歪みがあって。あの一件があって、自分がどういうスタンスをデザイナーとして持つのかというのは凄く大切だと思ったし、NOならNOという姿勢を貫いて、NOという立場で別の活動をすれば良ったんじゃないかと今だったら思うし、その経験が自分のいまのデザインの活動に活きている感じがあります。もちろん、子育てによって時間がないから取捨選択しているということもあるけど、それだけじゃなく、エンブレム問題によって、「何を」「誰と」ともにするのかということは自分でしっかり選ばないといけないんだと思いました。
原田:実はそこは地続きなんですよね。出産、妊娠、子育てと身の回りのことと、社会に関わることというのは全然別のことではないというか。
山田:そこがどんどん乖離してしまったのかなというのはありますよね。乖離したままの人たちもまだ一定数いて、でもそうじゃないぞという社会の変化の兆しはあるのかなと思うし、やっぱり社会を変えていくためにも言葉を紡いでいかないと何も変わらないと言うか。やっぱり「察して下さい」という文化では……。
原田:あまりにもそれで来すぎてしまったというのがありますよね。
山田:こんなことを言うと身も蓋もないですが、デザイナーの人たちが「言葉を発さないことがカッコ良い」と自分たちのことを思っていたところがあるのかなと。別に気取っているわけじゃないけど、言わなくても伝わるし、それがいいんだとされてきたというか。そうした時代の総決算みたいなところに五輪のエンブレム問題はある気がしていて。ドラスティックに社会の状況が変わってしまって、うまくそこにグラフィックが接続できていない部分もあるのかなという気はするんですよね。グラフィック自体、発表するメディアも表現も変わってきていて、その中ですごく大事にしないといけないこととかが。
カタチと言葉を行き来する
長嶋:私は建築の人たちと接点が増えたことで、デザインの考え方が結構変わったんですよね。グラフィックが建築と接点を持つのはサイン計画が多いのですが、サインというのは人の命がかかったりするし、建築自体もそうじゃないですか。
山田:守らなければいけないことが絶対にあるんですよね。
長嶋:そこには、なぜその形になったのか、なぜこの色になったのかということが、「意匠」も当然あるけど、それだけじゃない「機能」というもので、どう命を守るのかみたいなところは、建築の人たちは皆さんちゃんと考えていると思うし、構築的につくらないと形を紡げない分野だと思うから、そこは凄くしっかりやられている。そういう人たちの中に入っていった時に、あまりにも私が言葉を紡げなくてそのことを凄く指摘されたんですよね。これはなぜ良いのかという説明がそれじゃ全然理解できないと。しっかり言語化して伝えなきゃいけないというのは、彼ら・彼女らの姿勢を見ていて気づきがあった。デザインもひとつ間違えば誰かが死んでしまうかもしれないし、視覚障害の人からしたら凄く見えづらくてたどり着けないみたいなことも起きたりする。そういうところと密接な分野のデザインは説明責任が伴うと思いますが、一方で命が伴わないものはもっと無邪気でいられるから、言葉がいらなかったりするじゃないですか、感覚的なもので集約できたり。どちらかが良いとか悪いではないし、言語化ではなく感覚的なものによって成熟した文化というのもあるだろうけど、そういう違いが如実にグラフィックデザインの領域にはあって、その双方がもう少し行き来できると良いのかなとは思うんですけどね。
原田:自由に色と形と戯れられる無邪気さもグラフィックデザインの文化であるし、魅力でもあるので、それはそれでなくなるべきではないけれど、長嶋さんがおっしゃったような言語化をしていかなきゃいけないところとちゃんと行き来していくということが凄く重要ですよね。
山田:グラフィックが活躍できる場所はたくさんあって、もう駅貼りのポスターを志していた時代とは違う中で、それとは違う形でどう社会にコミットするのかというところですよね。その中に楽しさや喜びみたいなものももちろんあるべきだし、その両輪をちゃんと走らせていくことが凄く大事で、そのために言葉というのは重要な要素だと思いました。
原田:今日は「デザインと言語」「デザイナーの言葉」というテーマで色々お話を聴いてきました。その中で、デザイナーと社会の関わりについても伺えたかなと思います。次回が最終回となりますが、ここまでずっとデザインの「手前」の話をしてきた感じがするので、最後はデザインの話をしたいなと思います。それこそ長嶋さんが出産をされてつくるものがどう変わったのかということも含め、色々聞いていきたいと思っています。
山田:今日もありがとうございました。
長嶋:ありがとうございました。
最後までお読み頂きありがとうございました。
「デザインの手前」は、Apple Podcast、Spotifyをはじめ各種プラットフォームで配信中。ぜひ番組の登録をお願いします。
Apple Podcast
https://apple.co/3U5Eexi
Spotify
https://spoti.fi/3TB3lpW
各種SNSでも情報を発信しています。こちらもぜひフォローをお願いします。
Instagram
https://www.instagram.com/design_no_temae/
X
https://twitter.com/design_no_temae
note
https://note.com/design_no_temae